-

-
Google広告の使い方|2020年版最新情報や新しい機能などくわしく解説
この記事ではGoogle広告の使い方について解説します。Google広告の種類、アカウントの作成、キャンペーンの作成、広告グループの作成、広告の作成、広告の配信について、流れに沿ってわかりやすく説明。初めてGoogle広告のアカウントを作成や広告配信をする方におすすめです。
2020.11.09
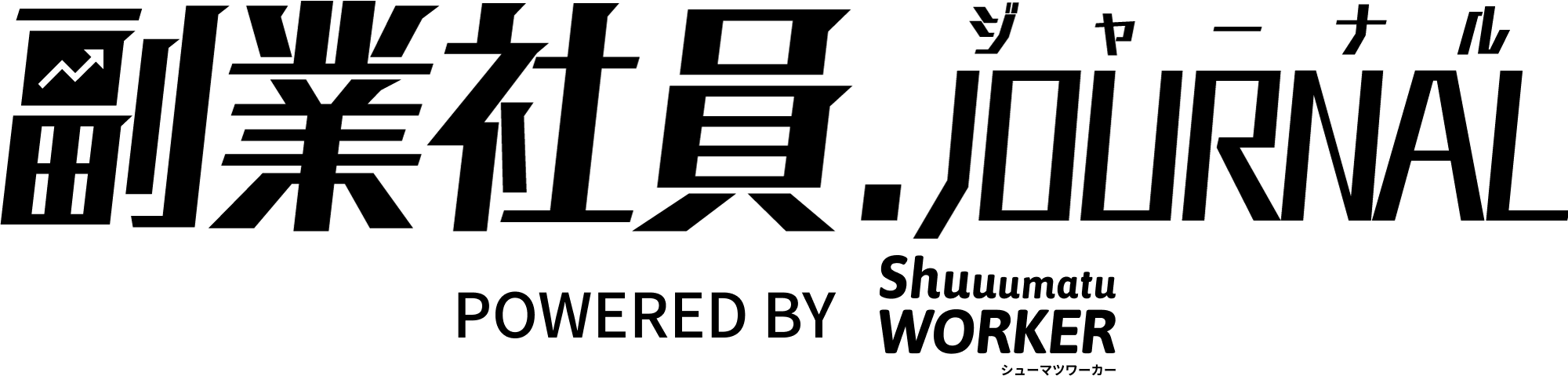
2025.10.30
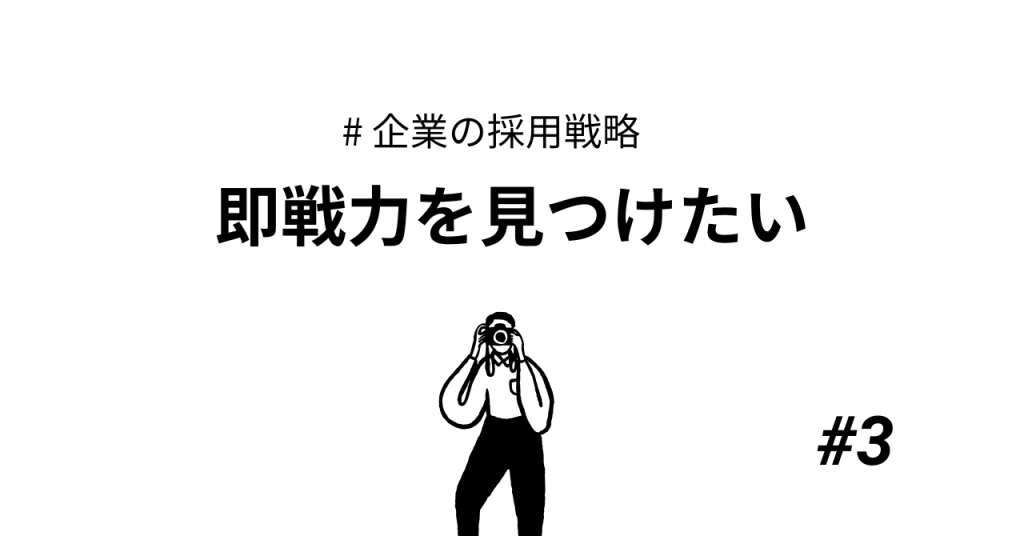
「即戦力人材が欲しい」という声は、中途人材採用で非常に多く聞かれます。しかし、実際に採用してみると「期待していたパフォーマンスが発揮されない」「早期に離職してしまった」というミスマッチが後を絶たないのも現実です。
こうした課題の背景には、従来の採用プロセスだけでは見極めきれない「即戦力の定義のあいまいさ」と「優秀な人材は転職市場にいない」という構造的な問題があります。
そこで近年、注目を集めているのが「副業→正社員採用」という新しい採用ルートです。本記事では、副業を活用した採用プロセスのメリットと具体的な実践について解説してまいります!
Contents
多くの企業が中途採用で「即戦力が欲しい」と口にします。しかし、「即戦力」とは具体的にどのような人材を指すのでしょうか。
即戦力人材を定義する際には、以下の3つの観点が必要です。
スキル面での定義
カルチャー面での定義
時間軸での定義
企業が即戦力を求める背景には、人材育成にかけるコストや時間を削減したいというニーズがあります。DX推進や新規事業立ち上げなど、事業スピードの加速が求められる現代において、すぐに活躍できる人材への需要は高まる一方です。特に中小企業では、教育体制が十分に整っていないケースも多く、「入社後すぐに結果を出してほしい」という切実な要望があります。
しかし問題は、この「即戦力」の定義があいまいなまま採用活動を進めてしまうケースが非常に多いことです。採用担当者自身が「どのようなスキルを持ち、どの程度の期間で、どんな成果を出せる人材」を求めているのか明確化できていないまま、面接を重ねてしまいます。
その結果、入社後に「思っていた人材と違った」という期待や認識のギャップが生まれ、早期離職につながってしまうのです。
中途採用におけるミスマッチの深刻さは、データからも明らかです。厚生労働省の「雇用動向調査」(*1)によると、2023年の離職率は15.4%に達しています。一般労働者の離職率は12.1%、パートタイム労働者では23.8%という水準です。特に入社3年以内の離職率は、大卒で約32.3%、高卒で約37%と、3人に1人が早期に離職している計算になります。
*1 厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/gaikyou.pdf
ミスマッチの主な原因は、以下の3点に集約されます。
書類や面接だけでは、実際の業務遂行能力を正確に測ることができません。特に実務経験やポートフォリオの解釈は難しく、面接での印象と実際のパフォーマンスにギャップが生じやすいのです。
価値観や働き方のスタイルが自社に合うかどうかは、短時間の面接では判断しきれません。前職では高評価だった人材が、環境が変わることで力を発揮できないケースもあります。
企業側が期待する成果と、応募者が認識している役割に乖離があることも少なくありません。このズレが入社後に顕在化し、双方にとって不幸な結果を招きます。
従来の中途採用プロセスには、構造的な限界があります。
履歴書や職務経歴書、面接での受け答えは、あくまでも「説明できる能力」であり、「実際にできる能力」とは異なります。特に専門職や管理職においては、プロジェクト管理能力、問題解決力、チームマネジメント力など、実際の業務を通じてしか測れないスキルが多数存在します。
面接での印象がいい人材が、必ずしも実務で高いパフォーマンスを発揮するとは限りません。逆に、面接が得意でない人材の中に、実は優秀な実務家が隠れていることもあります。
構造的課題2)試用期間の形骸化
多くの企業では3〜6ヶ月の試用期間を設けていますが、この期間が本来の目的を果たせていないケースが多く見られます。法的制約により、試用期間中でも解雇は容易ではなく、短期間で本質的な適性を見極めることも困難です。
結果として、試用期間は「形式的なもの」となり、採用判断の実質的な機会を逃してしまっています。
構造的課題3)「即戦力の定義」を採用プロセスで検証できていない
最も重要な問題は、採用プロセスの中で「自社にとっての即戦力とは何か」を具体的に検証する仕組みがないことです。面接で「この人は即戦力だ」と判断する根拠は、往々にして経歴や資格、面接での受け答えといった表面的な要素に限られています。
実際に自社の業務を任せてみて、どのような成果を出せるのか。チームとどのようにコミュニケーションを取るのか。こうした本質的な部分を、採用前に検証する手段がないのです。
中途採用における最大の構造的課題が、「優秀な人材ほど転職市場に出てこない」という現実です。
現職で高い評価を受け、活躍している優秀な人材は、そもそも転職を考える必要がありません。待遇も良く、やりがいもあり、成長機会もある環境にいる人材が、わざわざ求人サイトに登録したり、エージェントに相談したりすることは稀です。
仮にそうした人材が転職を考えたとしても、多くの場合は以下のルートで転職先が決まります。
つまり、公募の求人サイトに登録する前に、クローズドなネットワークの中で転職先が決まってしまうのです。
では、求人サイトに登録している人材や、エージェントを通じて応募してくる人材の質が低いかというと、必ずしもそうではありません。
こうした優秀な人材も確実に存在します。しかし、応募書類や面接だけでは、「前職で評価されなかった人材」と「環境が合わなかっただけの優秀な人材」を見分けることは困難です。判断材料が限られているため、結果として見極めに失敗するリスクが高まります。
こうした状況を打破するには、転職顕在層を待つ「待ちの採用」から、転職潜在層にアプローチする「攻めの採用」へのシフトが必要です。そして、その有効な手段の一つが、副業人材の活用なのです。
2018年は「副業元年」と呼ばれ、日本における副業推進の大きな転換点となりました。厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(*2) を策定し、モデル就業規則から副業禁止規定を削除したことで、企業が正当な理由なく副業を禁止することが難しくなったのです。
*2 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf
さらに2020年の改定では、企業と労働者の双方が安心して副業・兼業を行えるよう、労働時間管理のルールが明確化されました。そして2022年の改定では、副業を希望する労働者が適切な職業選択を通じて多様なキャリア形成を図ることを促進する内容へと発展しています。
こうした政府の後押しを受けて、副業を容認する企業は急速に増加しています。パーソル総合研究所の「第三回 副業の実態・意識に関する定量調査」(2023年)(*3)によると、企業の副業容認率は60.9%に達し、2021年調査から5.9ポイント上昇しました。
*3 パーソル総合研究所の「第三回 副業の実態・意識に関する定量調査」
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/sidejob3/
経団連の「副業・兼業に関するアンケート調査」(2022年)(*4)では、回答企業の70.5%が副業を「認めている」(53.1%)または「認める予定」(17.5%)と回答しています。特に従業員数5000人以上の大企業では、8割以上が副業を容認しています。
*4 経団連「副業・兼業に関するアンケート調査結果」
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2022/1027_04.html
副業が「仕方なく認めるもの」から、「企業にとってもメリットがあるもの」へと認識が変化してきている流れがあるのです。
近年、実際に副業を行っている会社員の割合は微増している一方、副業をしたいと考えている人(副業意向率)は40%以上に達しているという調査もあり、潜在的なニーズは非常に高いことがわかります。
副業人材の大きな特徴は、「現職で活躍している優秀な人材」が多く含まれている点です。彼らが副業を行う理由は以下のようなものです。
つまり、副業市場には「転職は考えていないが、新しい挑戦をしたい」という優秀な人材が多数存在しているのです。これは、通常の転職市場では出会えない人材層です。
優秀層に出会う方法の一つとして副業人材市場を紹介しましたが、副業を経由した採用プロセスには、従来の採用手法にはない多くのメリットがあるので、ここでは6つにわけて紹介していきます。
副業活用の最大のメリットは、「自社にとっての即戦力とは何か」を具体的に定義し、実務を通じて検証できる点です。
プロジェクトを通じた要件の具体化
実際のプロジェクトを副業人材と進めることで、当初漠然としていた「即戦力」の定義が、具体的なスキルセットや行動特性として明確になります。
例えば、「マーケティングの即戦力」を募集していた企業が、実際に副業人材と働いてみることで、「自社が本当に必要としているのは、戦略立案力ではなく、現場での実行力とデータ分析力だった」と気づくケースがあります。
期待値の擦り合わせ
副業期間中に、企業側が期待する成果と、人材が実際に提供できる価値を段階的に擦り合わせることができます。この過程で、双方の認識のズレを早期に発見し、修正できるため、正社員採用後のミスマッチを大幅に減らせます。
採用要件の精緻化
副業人材との協働を通じて得られた知見は、今後の採用活動にも活かすことができます。「即戦力」の具体的な定義が明確になることで、採用要件の精緻化が進み、より効果的な採用活動が可能になります。
面接では測れない実践力を、実際の業務を通じて可視化できることも大きなメリットです。
プロジェクトベースでの成果評価
副業人材には、通常、明確な成果物や目標が設定されたプロジェクトを任せます。この過程で、以下のような実務能力を直接評価できます。
職種別の評価例
面接での「できます」という言葉ではなく、実際の「できた」という実績で評価できるため、採用の確実性が格段に高まります。
副業期間は、企業と人材の双方が、お互いを深く理解する貴重な機会となります。
企業文化・働き方の相互確認
実際に一緒に働くことで、以下のような企業文化との相性を確認できます。人材側も、自分がこの環境で長く働けるか、やりがいを感じられるかを実感を持って判断できます。
早期離職率の低減
副業経由での採用は、通常の採用と比較して早期離職率が低いことが報告されています。これは、入社前に十分な相互理解が進んでいるためです。
正社員として入社した時点で、すでに企業の内情を理解し、業務にも精通しているため、入社後のギャップが最小限に抑えられます。
副業を経由した採用は、採用失敗のリスクとコストを大幅に削減できます。
採用失敗時の損失額
2024年の中途採用にかかる年間費用は平均650.6万円 (*5) という調査があります。また、再度の採用活動費用、失敗した人材の人件費や教育コスト、業務の遅延や機会損失、既存社員への負担増加などを考え合わせると、1人の人材の採用の失敗や早期退職で、数百万円以上の損失が発生することも珍しくないという状況です。
*5 雇用や労働、キャリアに関する調査・研究メディア「キャリアリサーチLab」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250326_93514/
副業期間中のコスト構造
一方、副業人材の活用では、通常は時間単価や成果報酬での契約となります。正社員の人件費と比較して、以下のような特徴があります。
仮に相性が合わなかった場合でも、契約期間満了で関係を終了できるため、リスクは限定的です。
ROI(投資対効果)の向上
副業期間中に成果を出してもらいながら、同時に採用の見極めができるため、投資対効果は非常に高くなります。「お試し期間にも成果を出してもらえる」という点は、試用期間とは大きく異なる特徴です。
副業から正社員になった人材は、通常の中途採用と比較して、圧倒的に早く戦力化します。
通常の中途採用では、以下のような段階を経て戦力化していきます。合計で6ヶ月以上かかることも珍しくありません。
一方、副業から正社員になった人材は、すでに以下を習得しています。
そのため、正社員として入社した初日から、即戦力として活躍できる可能性が高いのです。
ある企業の事例では、通常の中途採用で6ヶ月かかっていた戦力化期間が、副業経由の採用では1ヶ月以内に短縮されたケースもあります。この差は、企業にとって非常に大きな価値を生み出します。
副業活用の戦略的なメリットが、通常の転職市場では出会えない人材層にアプローチできる点です。
現職で活躍中の優秀人材との接点
前述の通り、現職で高いパフォーマンスを発揮している優秀な人材は、通常の転職市場には出てきません。しかし、副業という形であれば、「転職は考えていないが、新しい挑戦はしてみたい」という人材と接点を持つことができます。
潜在層へのアプローチ
副業期間中に良好な関係を築き、企業の魅力を実感してもらうことで、転職潜在層を転職顕在層に変えることができます。当初は「転職する気はなかった」人材が、副業を通じて「この会社で正社員として働きたい」と考えるようになるケースは少なくありません。
中長期的な関係構築
副業として関係を持ち続けることで、数年後のタイミングで正社員として迎え入れることも可能です。転職のタイミングは人それぞれですが、良好な関係を維持しておくことで、いざ転職を考えた際の有力な選択肢となります。
独自の採用ルートの確保
リファラルや紹介に頼らず、自社独自の採用ルートを確立できることも大きな意義があります。副業を入口とした採用チャネルを持つことで、人材獲得競争で優位に立つことができます。
副業を活用した採用を成功させるには、明確なプロセスと適切な準備が必要です。重要なのが「副業でどのような業務を任せ、どのように評価するか」、そして正社員転換への企業側の意思が固まった段階からのステップです。
副業人材には、プロジェクト型の業務を任せることが望ましいです。プロジェクト型の業務では、以下が明確にできていることが重要です。
これらのすり合わせができており、副業メンバーが現職との兼ね合いで可能な範囲での条件(稼働時間・報酬など)が合意できれば、副業での稼働がスタートできます。
また、プロジェクト型の業務を任せることで、企業にとっては、明確な目標と期間の中で、副業メンバーの力量や実際の実務能力、調整能力や業務遂行力、スキルやアウトプット力を見極めることができるため、この副業期間を採用に向けた有意義な期間にできます。
プロジェクトの期間中には、企業からの適切な評価やフィードバックも重要です。フィードバックに対して副業メンバーがどのように対応し、アウトプットに反映させるのかを見ることもできます。
次に難しいポイントとしては、正社員化の判断です。副業メンバーとは副業期間中、実際に一緒に働くことができるので、スキルや能力の判断は実務に基づいた判断ができる利点があります。
一方で重要なのがカルチャーフィットなど、ソフト面でのマッチ度合いです。そうした面も合わせて、副業メンバーに正社員として入社してほしいかどうか、社内で確認していきます。
また、副業期間中に、副業メンバーの将来的なキャリア意向と自社の方向性がマッチしているかといった、適性とのマッチを測るための情報を収集していくことも重要です。
まとめると、副業期間中に確認したいのは以下のポイントです。
副業メンバーと関係構築する中で、本人の意向を確認していくことも重要です。「今後、正社員として一緒に働くことに興味はありますか?」といった形で、まずは意向を探ります。双方が前向きであれば、具体的な条件交渉に進みます。
副業期間中の実績を踏まえて、適切な処遇を提示することが重要です。市場相場を考慮しつつ、本人の貢献度を反映した条件を提示しましょう。
あらかじめ月次や四半期でのチームリーダーと副業メンバーとの1on1などを設定しておくと、正社員採用に向けた副業メンバーの意向を確認するタイミングを作りやすくなります。
継続的な関係を維持したいため、交渉に移るのが難しいケースもあります。そういう場合には、あらかじめ正社員転換に向けた支援を受けることのできる副業エージェントサービスを利用することがおすすめです。
中途採用における「即戦力人材」の獲得は、多くの企業にとって重要な課題です。しかし、従来の採用プロセスには、即戦力の定義があいまいなまま進めてしまうこと、優秀な人材が転職市場に出てこないこと、面接だけでは実務能力を見極められないことなど、構造的な限界がありました。
【副業活用がもたらす5つの変革】
副業を活用した採用は、今後さらに拡大していくことが予想されます。政府の副業推進政策、副業容認企業の増加、副業人材市場の成熟により、この採用ルートは主流の一つとなっていくでしょう。特に、人材獲得競争が激しい職種や、即戦力が求められる中小企業にとって、副業活用は有力な選択肢となります。
副業を活用した採用を検討している企業は、小さなステップから始めてみることをおすすめします。
副業を活用した採用は、単なる採用手法の一つではなく、採用プロセス全体を見直す契機となります。「即戦力とは何か」を問い直し、実務を通じて人材を見極めるこのアプローチは、採用の確実性を高め、企業の競争力強化につながるでしょう。
転職顕在層を待つのではなく、転職潜在層にアプローチする。面接だけで判断するのではなく、実際に働いてもらって判断する。この新しい採用の形が、これからの時代のスタンダードになっていくはずです。
今こそ、副業を活用した採用プロセスの改善に、一歩踏み出してみませんか。
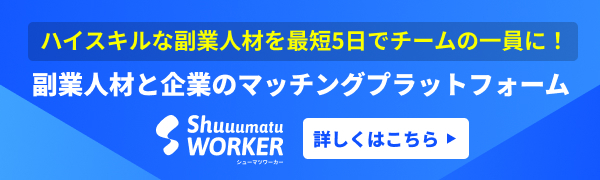
外部人材の活用について、お役立ち情報を掲載中です!