-

-
副業社員を正社員採用できるのか?
副業で手伝ってもらいつつ、そのまま正社員としてジョインしてもらうという話はよく聞きます…
2020.07.04
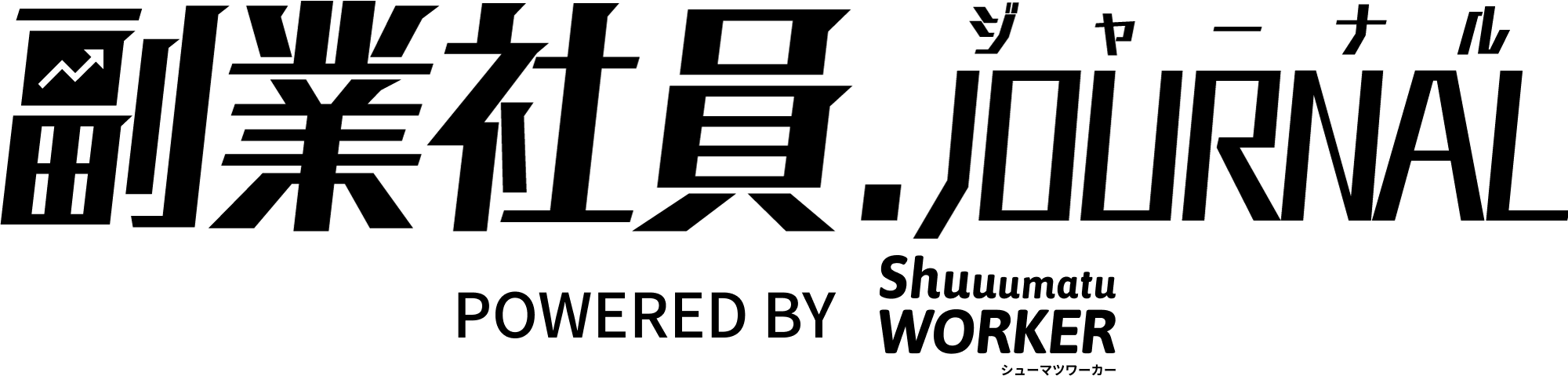
2025.10.22
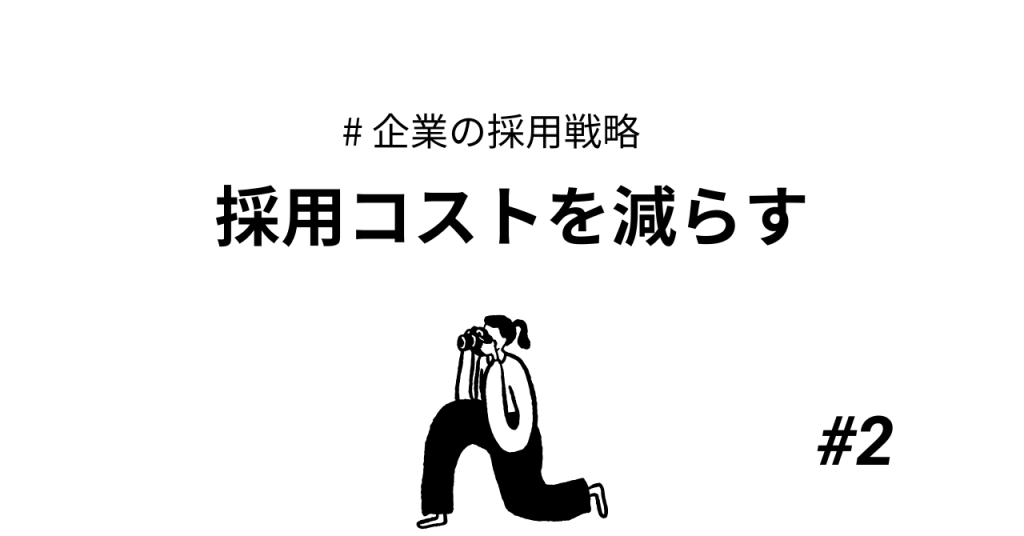
「採用コストが高騰しているが、人材の質は落とせない」
——多くの採用担当者やスタートアップ経営者が直面しているジレンマです。実際、2024年の中途採用にかかる年間費用は平均650.6万円と前年比20.9万円 (*1) 増加し、採用市場は依然として売り手市場が続いています。
*1 雇用や労働、キャリアに関する調査・研究メディア「キャリアリサーチLab」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250326_93514/
とはいえ、「コスト削減」と「人材の質」は決して相反するものではありません。
本記事では、採用コストを戦略的に削減しながら、必要な人材を確保するための「戦略的人材ポートフォリオ」の設計方法をご紹介します! 限られたリソースで最大の成果を上げる採用戦略を構築していくヒントになれば幸いです!
Contents
“採用コストの高騰”は、企業にとっても大きな課題であり続けています。雇用や労働、キャリアに関する調査・研究メディア「キャリアリサーチLab」で公開された株式会社マイナビの調査によると、2024年卒の新卒採用単価は56.8万円、中途採用においては1社あたり年間平均20.8人を採用するのに650.6万円のコストがかかっています。これは前年比で20.9万円の増加です。
職種によっても採用コストに大きな差があります。営業職では約41万円、事務職では約36万円と、専門性の高い職種ほど採用コストが高騰する傾向にあります。エンジニアやマーケターといった専門職では、さらに高額になるケースも珍しくありません。
企業規模別で見ると、2025年卒の採用費用が「増える見通し」と回答した企業は、大企業で52.9%、中小企業でも32.7% (*1) に達しています。つまり、企業規模を問わず、採用コストの上昇は全体的なトレンドとして定着しているのです。
採用コストが上昇し続けているのには、以下の3つの構造的な要因があります。
1. 労働人口の減少と売り手市場化
日本の労働人口は減少の一途 (*2) をたどり、特に若年層の人材獲得競争は激化しています。求職者が企業を選ぶ時代となり、企業側は給与水準の引き上げや福利厚生の充実、採用広告費の増額を余儀なくされています。この構造的な人材不足は、今後も長期的に続くことが予測されます。
*2 総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)」
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/gaiyou.pdf
2. 採用チャネルの多様化による管理コスト増
求人媒体、人材紹介、SNS採用、リファラル採用、ダイレクトリクルーティングなど、採用チャネルは年々多様化しています。一見すると選択肢が増えて良いように思えますが、実際には各チャネルの管理工数が増大し、効果測定が複雑化しています。「とりあえず複数の媒体に出しておく」という戦略では、費用対効果の悪いチャネルにコストをかけ続けるリスクが高まります。
3. 早期離職による「隠れたコスト」
採用コストを考える際、見落とされがちなのが早期離職によるコストです。採用した人材が数ヶ月から1年以内に退職してしまった場合、それまでにかけた採用費用だけでなく、教育研修コスト、引き継ぎコスト、そして再度採用活動を行うための追加コストが発生します。
統計データによれば、2023年の一般労働者の離職率: 12.1%で、離職理由では、「仕事の内容に興味を持てなかった」「職場の人間関係が好ましくなかった」など、ミスマッチによる離職の割合が上昇した (*3) ことが報告されています。採用コストの観点でも、採用プロセスにおける認識のすり合わせやカルチャーマッチなどの重要性が上がっているのです。
*3 厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/gaikyou.pdf
採用コストを効果的に削減するためには、まず自社がどのような「落とし穴」に陥っているかを認識することが重要です。ここでは、採用コストが膨らむ企業に共通する5つの失敗パターンを解説します。
「即戦力の人材がほしい」「優秀な人を採用したい」——こうした曖昧な要件で採用活動を進めていませんか。採用ターゲットが不明瞭なまま募集をかけると、本当に必要なスキルを持った人材には届かず、応募者の大半がミスマッチという事態に陥りかねません。
結果として、書類選考や面接にかかる工数が増大し、内部コストが膨らみます。さらに、採用後にも「思っていた人材と違った」というズレが生じ、早期離職につながるリスクも高まります。
必要なのは、具体的なペルソナ設計です。どのような業務を担当してもらうのか、そのために必要なスキルセットは何か、どのような価値観を持った人材が自社にフィットするのかを明確にする必要があります。
多くの企業が無意識のうちに陥っているのが、「すべての業務を正社員で埋めるべき」という思い込みです。しかし実際には、すべての業務が正社員雇用に適しているわけではありません。
プロジェクトベースで発生する業務、専門性が高く社内育成が困難な業務、繁閑の差が大きい業務などは、副業人材や業務委託を活用したほうが、コストパフォーマンスも品質も高くなるケースが多々あります。
経団連のデータでは、社外からの副業や業務委託の人材の受け入れについて、回答企業の30.2%が「認めている」または「認める予定」と答えた (*5) ということです。徐々に外部人材を活用した組織戦略が浸透する中、採用戦略の観点でも、外部人材の受け入れが重要な意味を持ち始めています。とはいえ実際に活用した実績がある企業は、別のデータではまだ低い水準であることもわかっています。まだ多くの企業が、この選択肢を十分に活用できていないのです。
*5 経団連「副業・兼業に関するアンケート調査結果」
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2022/1027_04.html
複数の求人媒体に同時掲載すれば、母集団形成に有利だろう——このような考えから、効果測定を行わずに複数のチャネルに出稿し続けている企業は少なくありません。
しかし、チャネルごとの応募数、応募単価、採用単価、採用後の定着率などをしっかり分析しなければ、費用対効果の低い媒体にも、高いコストを払い続けることになります。特にスタートアップや中小企業では、限られた予算を最も効果的なチャネルに集中投下することが重要です。
各チャネルのROI(投資対効果)を可視化し、定期的に見直すプロセスを組み込むことで、無駄な出費を大幅に削減できます。
採用コストというと、求人広告費や人材紹介の成功報酬といった「外部コスト」に目が行きがちです。しかし、実際には面接官の工数、採用管理ツールの利用料、応募者の交通費、内定者フォローにかかる人件費など、「内部コスト」も相当な金額になります。
特に採用業務が属人化している企業では、特定の社員に業務が集中し、本来の業務に支障が出ているケースもあります。こうした見えにくいコストを可視化することで、採用プロセス全体の最適化ポイントが見えてきます。
今必要なリソースを補填することに集中しすぎて、採用ブランディングや中長期的な採用戦略に投資できていない企業も多く見られます。
採用ブランディングが弱いと、求職者に企業の魅力が伝わらず、応募数を確保するために広告費を増やすしかありません。結果として、広告依存の悪循環に陥り、採用コストが高止まりしてしまいます。
一方、オウンドメディアやSNSでの情報発信、社員インタビューの公開、リファラル採用の仕組み作りといった施策は、初期投資こそ必要ですが、中長期的には採用コストを大きく削減する効果があります。
それでは、これらの「落とし穴」にはまらず、採用コストを抑えていく施策はどのようなものがあるでしょうか。ここではいくつかの施策例をみていき、本記事のテーマである「人材の質と採用コストの両立」を目指すための最適な方法を探っていきます。
採用要件の曖昧さは、採用コスト増大の最大の原因です。要件を以下の3段階で整理し、しっかりとした採用要件を設定することが、最初にやるべきことと言えるかもしれません。
この整理を行うことで、求人票の訴求ポイントが明確になり、ターゲット人材に届きやすくなります。また、選考時の判断基準も統一され、面接官によるブレが減少します。
現場社員へのヒアリングを行い、「実際にどのようなスキルが必要か」「どのような人が活躍しているか」を具体的に把握することが、精度の高い要件定義につながります。
採用コストを中長期的に削減するには、採用ブランディングへの投資が欠かせません。
オウンドメディア・採用サイト 求人広告に頼らず、自社のメッセージを発信できる場を持つことは、採用ブランディングの基本です。事業のビジョン、大切にしている価値観、働くメンバーの声などを丁寧に伝えることで、「この会社で働きたい」と感じてもらえる確率が高まります。
社員インタビュー・note発信 社員一人ひとりのストーリーを発信することは、企業の「顔」を見せる効果的な方法です。特にスタートアップでは、創業メンバーや初期メンバーの熱量が伝わることで、共感する人材を引き寄せます。
noteやブログで、日々の業務の裏側や意思決定のプロセスを発信することも有効です。透明性の高い情報発信は、信頼感を醸成し、ミスマッチの少ない応募につながります。
採用ブランディングの強化は、短期的には効果が見えにくいかもしれませんが、1〜2年のスパンで見ると、応募の質と量が大きく向上し、結果的に採用単価を大幅に下げる効果があります。
採用担当者が手作業で行っていた応募者とのメールのやり取り、Excelでの管理、面接官へのスケジュール確認など、内部コストをしっかり見える化することで、どの業務を効率化し、どのように採用業務にかかる工数を削減すべきか明確になります。
内部コストを削減するには、採用管理システム(ATS: Applicant Tracking System)の導入という選択肢もあります。ATSは、応募者情報の一元管理、選考ステータスの可視化、面接日程の自動調整、評価シートのテンプレート化などの機能を提供するツールです。
採用活動を「なんとなく」行っている限り、コスト削減は実現できません。数値で効果を測定し、PDCAを回す仕組みが必要です。
設定すべき主要KPIには、例えば以下のようなものがあります。
企業の状況や求めている姿に合った指標をモニタリングし、課題があれば速やかに対策を打ちます。
特に重要なのが「採用チャネルの最適化」です。例えば、ある媒体からの応募単価が高い割に採用単価も高い場合、その媒体は費用対効果が低いと判断し、予算を他のチャネルに振り分けるといった判断ができます。
施策5:戦略的な人材ポートフォリオの活用と副業・業務委託人材の戦略的活用
業務を棚卸しし、最適な雇用形態をマッピングしていく方法です。
この施策については次章で詳しく紹介していきます!
採用コストを削減しながら最適な人材を確保するための施策として、前章で紹介した「戦略的な人材ポートフォリオ」の設計を、より詳しくみていきましょう。
人材ポートフォリオを戦略的に使うことで、「すべての業務やリソースを正社員で」と固定的に考えるのではなく、業務の性質に応じて最適な雇用形態を使い分け、その結果として採用コストの大幅減を実現していきます。
「人材ポートフォリオ」を設計する際の基本的な考え方は、業務を以下の3つの軸で分類することです。
軸1:コア業務 vs ノンコア業務
コア業務とは、企業の競争優位性を生み出す中核的な業務です。例えば、プロダクト開発、営業戦略、顧客との関係構築などが該当します。これらは基本的に正社員の人材が担当し、組織のノウハウとして蓄積していきたい領域です。
一方、ノンコア業務は重要ではあるものの、競争優位性に直結しない業務です。経理処理、一部のバックオフィス業務、定型的なマーケティング施策の遂行などが該当します。こうした領域は、業務委託や副業人材の活用が適しています。
軸2:恒常的業務 vs プロジェクト型業務
年間を通じて継続的に発生する業務は正社員での対応が合理的です。一方、新規事業の立ち上げ、システムリニューアル、キャンペーン実施など、期間限定で発生する業務は、「プロジェクト単位」で業務委託契約を結ぶほうが柔軟かつコスト効率的です。
軸3:育成前提 vs 即戦力必須
長期的に育成し、将来の幹部候補として期待する人材は正社員採用が適しています。しかし、高度な専門性が必要で、かつ社内に育成ノウハウがない領域(例:データ分析、UI/UXデザイン、SEO対策など)では、既にスキルを持った副業人材や業務委託を活用するほうが、採用コストも育成コストも抑えられます。
以下で、これらの軸を組み合わせて業務を分類してみました!
【業務分類マトリクス例】
副業人材や業務委託の活用は、単なるコスト削減策ではなく、適切に活用すれば、人材の質、柔軟性、スピード感のすべてにおいてメリットがあります。
固定費を変動費化できることをメリットに挙げられます。正社員を1名雇用する場合、給与に加えて社会保険料(約15%)、賞与、退職金積立、福利厚生費などが発生し、総額では給与の1.5〜2倍程度の費用が必要になります。
業務委託では、必要な業務量に応じた報酬のみを支払えばよく、社会保険料などの法定福利費は不要で、固定費だった人材費の変動費化ができます。
「業務委託は正社員より質が低い」という思い込みは誤りです。むしろ、副業市場には大企業で実績を積んだ優秀な人材が多数参加しています。
働き方の多様化により、大手企業の現役社員がスキルアップや収入増を目的に副業を始めるケースが増えています。こうした人材は、本業で培った高度な専門知識や大規模プロジェクトの経験を持っており、スタートアップや中小企業では正社員として採用することが困難な人材層です。昨今の副業人材は単なる補助的な業務だけでなく、事業戦略や新規事業開発といったコア業務でも活躍しています
ビジネス環境の変化が激しい現代において、柔軟性は重要な競争力です。業務委託であれば、繁忙期には稼働を増やし、閑散期には減らすといった調整が可能です。
また、新規事業や新しい施策を試す際、いきなり正社員を採用するのはリスクが高すぎます。まずは業務委託でプロジェクトを進め、うまくいけば規模を拡大し、必要に応じて正社員化するという段階的なアプローチが取れます。
さらに、万が一ミスマッチが発生した場合でも、正社員と比較して契約の見直しがしやすいという点も見逃せません。正社員の場合、採用後のミスマッチは企業にとっても本人にとっても大きな負担となりますが、業務委託であれば比較的柔軟に対応できます。
こうしたメリットも考えると、企業の採用戦略における選択肢の一つとして、副業・業務委託人材の活用を取り入れていくことは、単に採用コストの削減のためだけではなく、組織の将来性を広げるためにもますます有意義であることがわかります。
採用コストの削減と優秀な人材の確保は、決して相反するものではありません。「すべてを正社員で」という固定観念が、この両立を妨げる一因になってはいないでしょうか。本記事でご紹介した「戦略的な人材ポートフォリオ」のアプローチを取り入れると、採用コストを大幅に削減しながら、必要な専門性を持った人材を確保できていきます。
副業人材や業務委託の活用は、単なるコスト削減策ではなく、組織を柔軟で強くするための戦略的な選択です。トライアルとして小さく始めて、効果を確認しながら段階的に拡大していくことで、自社にとって最適な人材戦略を構築できるはずです。
業務の性質に応じた最適な人材配置ーー企業の組織戦略・採用戦略に、この考え方を根付かせていくことこそが、採用コスト削減を実現する近道かもしれません。
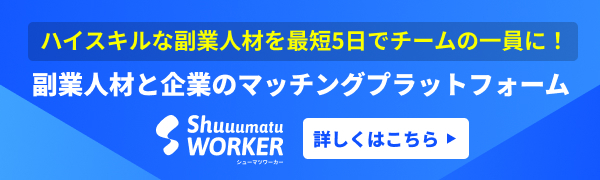
外部人材の活用について、お役立ち情報を掲載中です!