-
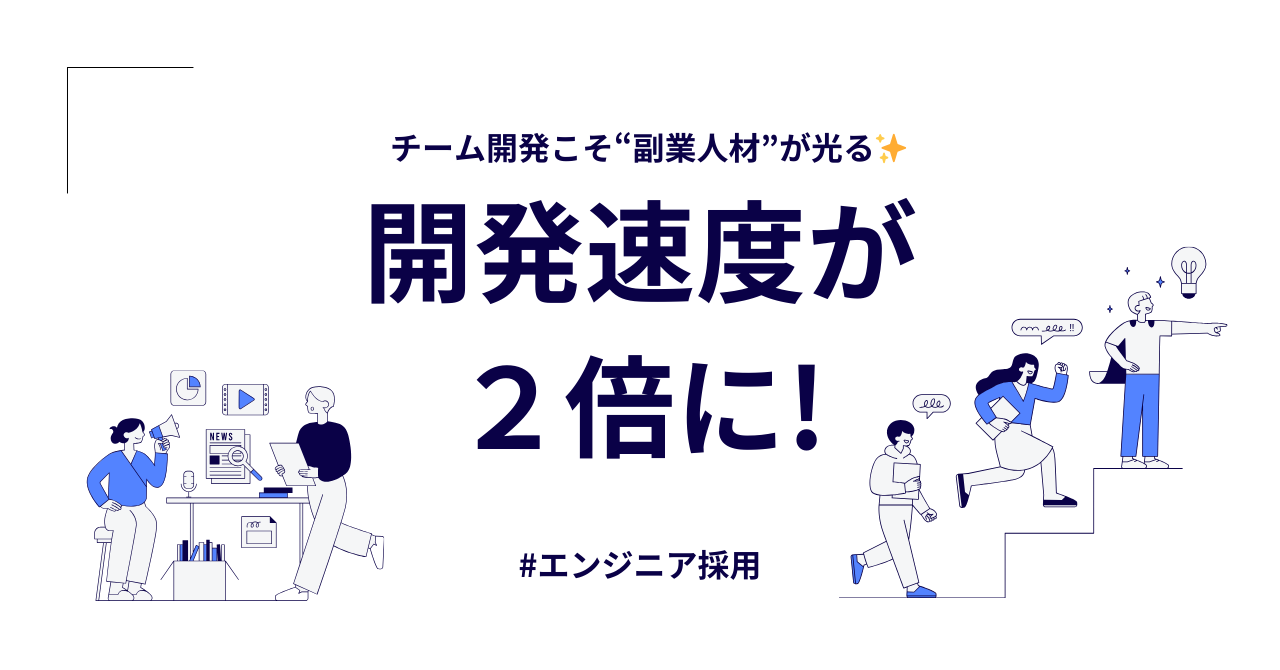
-
【チーム開発こそ副業人材が活躍】採用力に課題があっても、副業エンジニアの力で開発スピード2倍へ!
2025.12.18
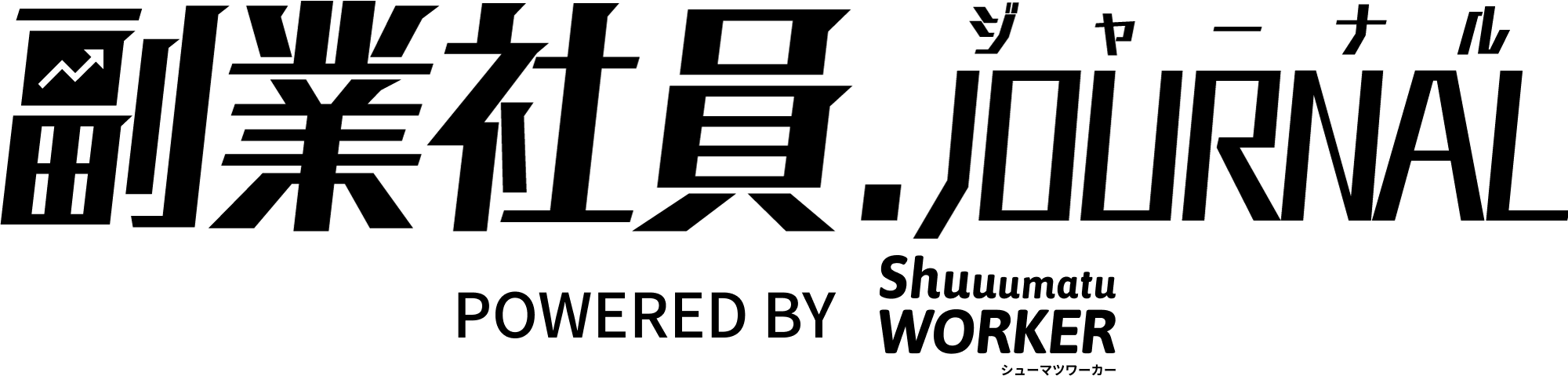
2025.11.28
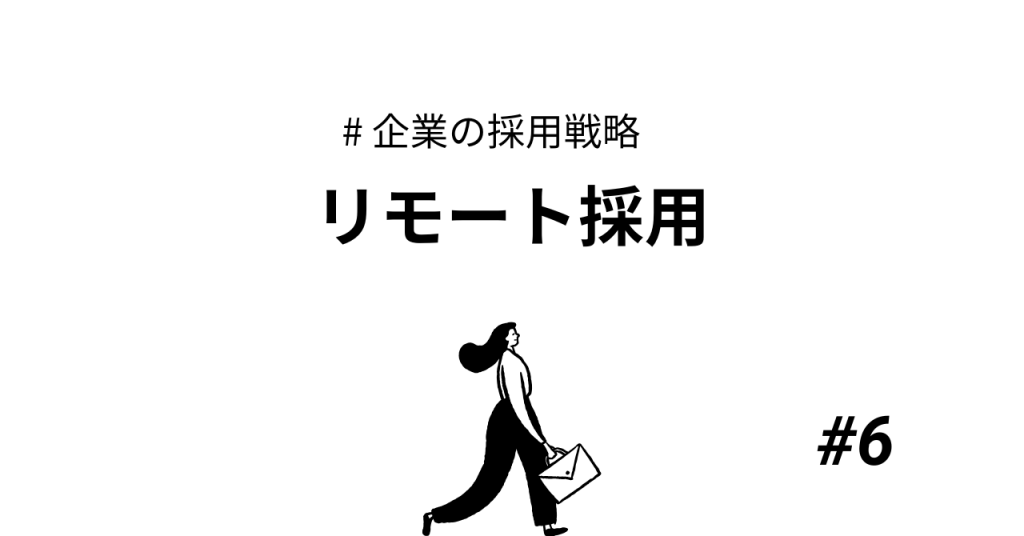
新型コロナウイルスの影響を機に急速に広がったリモート採用。
感染症の5類移行後も、リモートワーク求人は増加を続けています。オンライン面接は、もはや一時的な対応策ではなく、採用活動における重要な選択肢として定着しつつあります。
とはいえ、「オンライン面接では候補者の本質を見極めにくい」「入社後のミスマッチが心配」といった不安を抱える採用担当者の方も多いのではないでしょうか。実際、人事担当者の約7割がオンライン選考よりも対面が好ましいと感じており、約8割がオンライン選考のほうが入社後ミスマッチが多いと回答しているというデータもあるようです。
この記事では、リモート採用における課題を整理し、オンライン面接を成功させるための具体的な7つの方法をご紹介します。リモート採用の課題を乗り越え、優秀な人材との出会いを実現するヒントになれば幸いです。
Contents
2025年12月時点で、全国のテレワーク利用率は14%、東京圏では22%という調査報告があります(*1)。コロナ禍のピーク時と比較すると減少しているものの、リモートワーク求人は増加傾向にあり、企業と求職者の双方がリモート採用を一つの選択肢として認識していることがわかります。
*1 「第3回デジタル経済・社会に関する就業者実態調査」(NIRA総合研究開発機構)https://www.nira.or.jp/paper/research-report/2025/212510.html
特に注目すべきは、リモートワーク求人の割合です。2024年9月には2023年1月と比較して約1.5倍に増加しており、5類移行後も減少することなく、むしろ増加を続けています。これは、企業がリモート採用を戦略的に活用し始めている証拠といえるでしょう。
*2 「リモートワーク(ハイブリッドワーク・フルリモート)の実態調査」(パーソルキャリア株式会社)https://doda.jp/guide/ranking/102.html
リモート採用には多くのメリットがある一方で、企業は以下のような課題に直面しています。
課題① 候補者の見極めが難しい
オンライン面接では、対面と比較して候補者の表情や雰囲気を読み取ることが難しくなります。実際、「オンライン面接のみでは適切な選考が難しい」と回答した企業は9割以上という調査(「非常にそう思う」が32.4%、「ややそう思う」が59.5%となり、合計すると91.9% *3)もあり、最も多くの企業が抱える課題となっています。
*3 「オンライン面接での採用前後のギャップに関する実態調査」(出典元:採用に関する情報メディアmoovy)https://moovy.jp/
細やかな表情や身振り手振り、その場の空気感など、対面であれば自然に感じ取れる情報が限られてしまうため、候補者の本質的な人柄やコミュニケーション能力を判断しにくいという声が多く聞かれます。
課題② 入社後のミスマッチが増加する懸念
オンライン選考では、企業と候補者の相互理解が不十分になりがちです。人事担当者の約8割がオンライン選考のほうが入社後ミスマッチが多いと感じており(*3 前述)、この懸念は無視できません。
候補者側からも「企業や社員の雰囲気が分かりにくい」という声が多く、双方にとって不完全な情報のまま採用判断を下すリスクが高まっています。職場の雰囲気や企業文化といった、言葉では伝えきれない要素が伝わりにくいことが、ミスマッチの一因となっています。
課題③ 技術的なトラブルと運用ノウハウの不足
オンライン面接を実施した企業には「応募者の声が聞こえないなどの音声トラブル」を経験している企業(*4)もあり、回線トラブルを経験する企業や、リモート環境に慣れない候補者・企業担当者への配慮が必要だという調査結果もあり、これはコロナ禍での調査ではありましたが、技術的な問題も、オンライン面接では気にかける必要のある要因と言えます。
*4 「「オンライン面接」実態調査『人事のミカタ』アンケート」(エン・ジャパン株式会社)https://www.atpress.ne.jp/news/232953
また、オンライン面接のノウハウや運用方法はこの数年で広まってきたものであり、新しい採用手法への対応に苦慮している企業も多いかもしれません。
それでは、リモート採用を成功させるために特に重要な3つのポイントを見てみましょう。
オンライン面接は、候補者を評価する「見極め」の場であると同時に、候補者に自社の魅力を伝え、志望度を高める「動機づけ」の場でもあります。
対面と比較して、オンラインでは企業の魅力が伝わりにくいという課題があるため、一方的な質問攻めにならないよう注意することが必要です。候補者の質問時間を十分に確保し、双方向のコミュニケーションを心がけることがポイントになります。
リモート採用の手法は、まだ発展途上です。定期的に採用プロセスを振り返り、改善していく仕組みを作っていくこともポイントです。
これらのデータを蓄積し、PDCAサイクルを回すことで、自社に最適なリモート採用の形を見つけることができます。
必ずしもすべての選考プロセスをオンラインで完結させる必要はありません。初回面接はオンラインで効率的に実施し、最終面接は対面で実施するなど、ハイブリッド型の選考プロセスも効果的です。
特に、カルチャーフィットが重要なポジションや、入社後のミスマッチリスクが高い場合には、少なくとも1回は対面での面接機会を設けることはオススメできます。その場合、遠方の候補者には交通費を支給するなど、柔軟な対応を検討しましょう。
それでは、これらの課題を乗り越え、リモート採用を成功させるためのポイントも考慮しつつ、リモート採用を成功させるための具体的な方法を見ていきましょう。
オンライン面接では対面よりも限られた情報で判断する必要があるため、事前に採用要件を明確にしておくことが極めて重要です。採用要件を以下の3段階で整理しましょう。
Must(必須条件) 業務遂行に不可欠なスキルや経験を定義します。「Webマーケティング実務経験3年以上」「SQLを使ったデータ抽出ができる」など、これを満たしていない場合は絶対に採用しないという基準です。
Want(歓迎条件) あれば望ましいが、なくても育成や他のメンバーでカバーできる項目です。「BtoBマーケティング経験」「Googleアナリティクス認定資格保有」などが該当します。
Better(あったら尚良い) 直接的には必須ではないが、あると業務がスムーズになる項目です。「スタートアップでの就業経験」「英語でのコミュニケーション能力」などです。
この整理により、面接での評価基準が明確になり、面接官による判断のブレが減少します。特にオンライン面接では時間が限られるため、どのポイントに注目して質問するかを事前に設計しておくことが成功の鍵となります。
オンライン面接では、主観的な印象に左右されやすくなります。これを防ぐために、構造化面接の導入が効果的です。
構造化面接とは、あらかじめ決められた質問項目と評価基準に基づいて面接を行う手法です。具体的には以下のステップで実施します。
構造化面接により、候補者間の公平な比較が可能になり、「なんとなく良さそう」という曖昧な判断を避けることができます。
オンライン面接だけでは見極めが難しいという課題に対しては、段階的な選考プロセスを設計することが有効です。
このように段階を踏むことで、限られた情報から判断するリスクを軽減し、候補者との相互理解を深めることができます。
技術的なトラブルは面接の質を大きく下げる要因となります。以下のチェックリストを活用し、万全の準備を整えましょう。
企業側の事前準備
候補者へのサポート
また、面接中にトラブルが発生した場合の対応フローも事前に決めておきましょう。音声が途切れた場合、画面が固まった場合など、想定されるトラブルごとに対応方法を準備しておくと、慌てずに対処できます。
オンライン面接では、候補者と対面で合う場合と比べて雑談などの機会が限られるため、相手の本音を引き出したり、面接の中で十分に言葉を引き出すことが難しくなる場合が多いです。そこで活用できるのが、採用領域でこれまでも研究されてきた、面接で候補者の言葉を引き出すための質問技法です。
STAR法による深掘り質問
この質問法により、候補者の具体的な経験と思考プロセスを深く理解することができます。
オープンクエスチョンの活用
「はい/いいえ」で答えられる質問(クローズドクエスチョン)ではなく、候補者が自由に回答できる質問(オープンクエスチョン)を多用しましょう。
例:
沈黙を恐れず「待つ」
オンラインでは沈黙が気まずく感じやすいため、面接官が次々と質問してしまいがちです。しかし、候補者に考える時間を与えることで、より深い回答を引き出すことができます。
入社後のミスマッチを防ぐためには、企業の文化や職場の雰囲気を具体的に伝えることが重要です。
バーチャルオフィスツアーの実施 実際のオフィスや作業環境をカメラで映しながら案内します。リモートワーク中心の企業であれば、チームメンバーの自宅作業環境を紹介するのも良いでしょう。
現場メンバーとの座談会 実際に一緒に働くメンバーとのカジュアルな座談会を設定します。複数名のメンバーが参加することで、チームの雰囲気や関係性が伝わりやすくなります。
動画コンテンツの活用 社員インタビュー動画や1日の業務の流れを紹介する動画などを事前に共有し、候補者が企業のリアルな姿をイメージできるようにします。
具体的なエピソードを共有する 抽象的な表現(「風通しの良い職場」「チームワークを重視」)ではなく、具体的なエピソードを共有しましょう。
例:
最も確実にミスマッチを防ぐ方法は、「実際に一緒に働いてみる」ことです。正社員として採用する前に、副業や業務委託という形で一定期間協働し、相互の適性を確認するアプローチが注目されています。
副業・業務委託活用のメリット
オンライン面接だけでは見極めきれなかった候補者の実務能力、コミュニケーションスタイル、チームとの相性などを、実際の業務を通じて確認できます。実務能力、問題解決アプローチ、責任感、企業文化への適応力を実際に評価できるのです。
候補者側も企業の方針、チーム環境、業務の進め方を体験でき、入社後のギャップを最小限に抑えることができます。
また、万が一相性が良くない場合でも、正社員雇用と比較して契約終了のハードルが低く、双方にとって負担の少ない形で関係を終了できます。
具体的な活用方法
例えば、マーケティング人材の採用を検討する際、まずは3ヶ月の業務委託で特定のプロジェクトを依頼し、その成果と働きぶりを見て正社員化を判断するという方法があります。
この期間中に、企業側は候補者のスキルレベル、創造性、責任感、企業文化への適応力を実際に確認でき、候補者側も企業の方針、チーム環境、業務の進め方を体験できます。
副業市場には、現在の職場に満足しているものの、新しいチャレンジや副収入を求める優秀な人材が多数存在します。これらの人材は、従来の転職市場には現れないため、正社員採用のみに頼っていては出会うことができません。
オンライン面接での見極めに限界を感じている企業にとって、副業・業務委託を活用したアプローチは、採用リスクを大幅に軽減する有効な戦略といえるでしょう。
リモート採用は、地理的な制約を超えて優秀な人材と出会える可能性を広げる一方で、見極めの難しさやミスマッチのリスクといった課題も抱えています。
しかし、本記事でご紹介した7つの方法を実践することで、これらの課題を克服し、リモート採用を成功させることが可能です。
特に、副業・業務委託を活用した「実際に一緒に働いてみる」アプローチは、オンライン面接だけでは見極めきれない部分を補完する強力な手法です。まずは小さなプロジェクトから始め、その効果を実感してみることをおすすめします。
シューマツワーカーなら、専任の担当者が、一緒に副業・業務委託のプロジェクトを検討し、募集案件の作成までお手伝いします。初めての副業・業務委託活用での採用アプローチを検討しているならば、ぜひ一度ご相談ください!
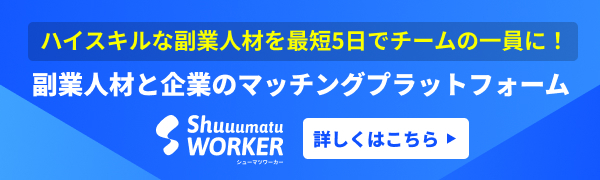
外部人材の活用について、お役立ち情報を掲載中です!