-

-
Google広告の種類|それぞれの仕組みや特徴、出稿までの流れなど紹介します
この記事ではGoogle広告の種類について解説します。課金方式、リスティング広告、ディスプレイ広告、Google動画広告(Youtube広告)、ショッピング広告、アプリキャンペーンのメリットや注意点について紹介するとともに、Google広告の配信方法や注意点も合わせてご紹介します。
2020.11.09
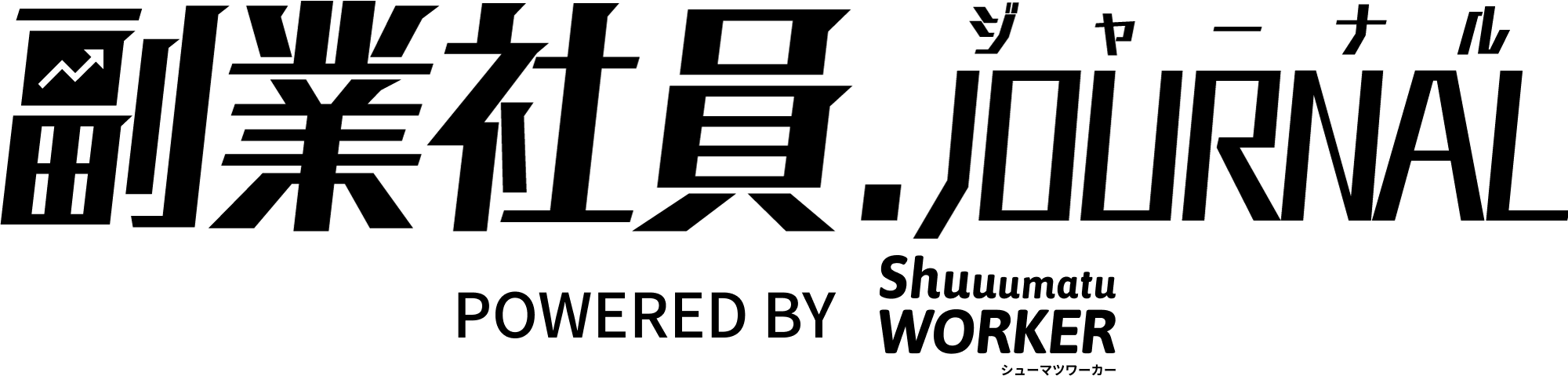
2025.10.17
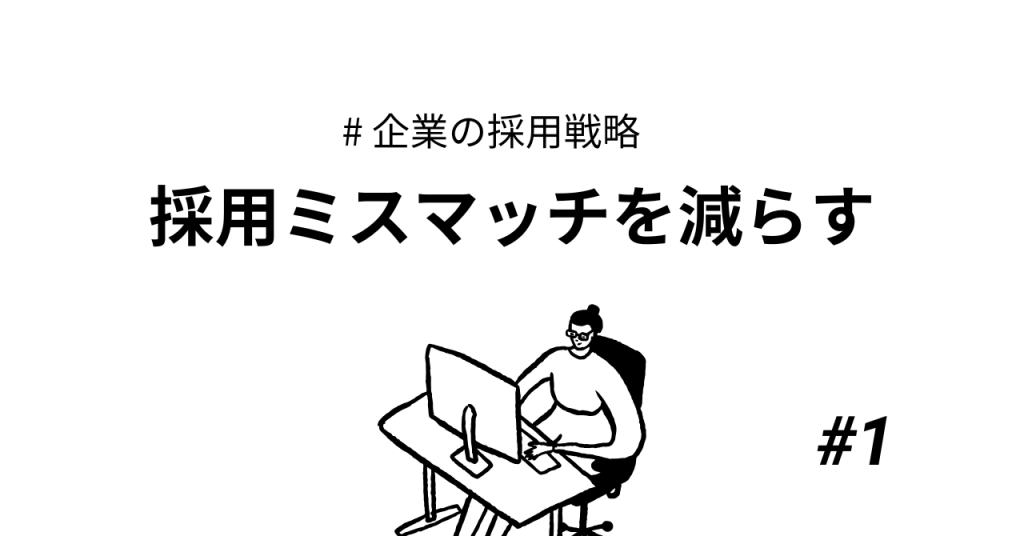
「今度こそ長く活躍してくれる人材を採用できた」
と安堵したのも束の間、入社3ヶ月で退職届を提出される―。このような経験をお持ちの人事担当者の方は決して少なくないのではないでしょうか。
厚生労働省が令和6年に発表した「新規学卒就職者の離職状況*」によると、大学卒業者の34.9%が入社から3年以内に離職しており、採用活動にかけた時間とコストが無駄になってしまうケースが後を絶ちません。これは新卒入社者のデータですが、中途採用で転職し入社した人材においても、早期離職は多くの企業にとって大きな問題となっています。
*厚労省「新規学卒就職者の離職状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html
「正社員採用」では、書類選考と数回の面接だけで「この人なら大丈夫」という判断を下さなければならず、入社後に「思っていた人材と違った」「社風に合わない」といったミスマッチが発生するリスクは避けられません。
この記事では、採用ミスマッチの原因に焦点を当てて、そのリスクや解決方法を紹介してまいります。
Contents
採用におけるミスマッチは、大きく分けて「スキルミスマッチ」と「カルチャーミスマッチ」の2つに分類されます。
「スキルミスマッチ」は、企業が想定している業務に必要とされるスキルと、採用候補者の持つ能力・経験・知識が合わないというケースです。
例えば、「営業経験5年」という経歴を持つ人材でも、前職が既存顧客への深耕営業中心だった場合、新規開拓が主体の企業では十分な成果を出せない可能性があります。また、「マーケティング経験者」でも、BtoCの消費財マーケティングの経験者がBtoBのSaaS企業で活躍するには、異なるスキルセットが必要になるケースも少なくありません。
一方、「カルチャーミスマッチ」は、個人の価値観や働き方に対する考え方と、企業の文化や組織風土とが合わないというケースです。
スキル面では申し分なくても、コミュニケーションスタイルや仕事の成果への考え方などが合わないと、入社者がうまく自分の力を発揮できなかったり、企業が求める成果が出てこないということが起こります。
ここで注目したいのは、短期的な成果に影響するのは主にスキルミスマッチですが、長期的な定着率や組織への貢献度により大きな影響を与えるのは、カルチャーミスマッチだといわれていることです。実際、入社後3年以内の離職理由を調査すると「人間関係」「社風が合わない」といったカルチャー面の問題が上位を占めることが多いのです。
採用のミスマッチが企業にもたらすリスクやデメリットはたくさんあります。ミスマッチが起きて早期退職が生じた場合にも、その社員が組織にとどまる場合にも、企業としては見逃せないコストを払うことになってしまうのです。ここでは、具体的なリスクをご紹介します。
採用ミスマッチの最も分かりやすい影響は、早期退職が生じた場合の「金銭的な損失」です。
一人の採用にかかる直接費用(求人広告費、人材紹介手数料、面接実施費用など)に加えて、研修費用、入社手続きコスト、さらには早期離職が発生した場合の再採用費用まで含めると、その損失額は想像以上に大きくなります。
中途採用の場合、人材紹介会社への成功報酬は年収の30-35%が相場なので、年収500万円の人材であれば150万円以上の紹介手数料がかかります。入社後の研修・指導コスト、業務引継ぎのための既存社員の時間コストを考慮すると、一人当たりの採用関連費用は200万円を超える計算になります。
一人の人材を採用するにあたって、ミスマッチが原因で早期退職が生じると、多くのコストが無駄になり、損失が生じてしまうのです。
早期離職が発生した場合には、「機会損失」も生じます。その人材に期待していた事業における成果、例えば事業成長や目標に向けた事業展開が実現できなくなってしまいます。リソース不足を補填するために採用活動をしていた場合には、再び採用活動を開始するまでに空白期間が生まれ、業務が停滞してしまうリスクもあります。
また、スキルのミスマッチが起きた場合には、その人材が期待する業務を遂行するスキルがないことがわかっても、企業側から簡単に入社を取りやめるということはできません。社員に対しての追加の研修やトレーニングが必要になることもありますし、目的を達するまでに想定以上の時間がかかることになります。
採用ミスマッチがあると、採用された社員や企業の事業だけではなく、広く組織全体にも影響します。スキル不足や価値観の相違により期待された成果が出せない人材がいると、その業務を他のメンバーがフォローする必要が生じ、チーム全体の生産性が低下します。
社員が早期退職してしまった場合も同様に、モチベーション低下や業務をカバーする負担など、周囲への影響は必至です。
「早期退職」が繰り返されると、企業の「離職率」が上がってしまい、今後の採用力にも影響します。多くの優秀な人材が、多数の企業からスカウトをもらう現在の転職市場では、採用プロセスの中で企業は常に比較されます。その中で、「離職率」の高い企業が敬遠されることは間違いありません。
また転職口コミサイトやSNSの影響も無視できません。採用ミスマッチが引き起こす早期退職が、「離職率の高い企業」「人材を大切にしない会社」といったネガティブな評判を形成していく可能性があります。一度失った採用ブランドを回復するには長期間を要しますし、既存社員にとっても、「この会社は人の見る目がない」「採用基準が低い」という不信感を抱き、組織全体の士気低下につながる可能性もあります。
採用ミスマッチは企業だけでなく、個人にも大きな意味を持ってしまいます。
早期離職の場合には、短期間での転職回数を増やしてしまうことになり、その人材の次の転職活動やキャリア形成に不利益を与えます。採用のミスマッチが原因で、人材の市場価値を下げることに繋がるのです。
一方、社員がその企業にとどまる場合にも、スキルや価値観に合わない環境で働き続けることで、本来持っている能力を発揮できず、キャリア形成の機会を逸してしまうことがあります。また、そのストレスが精神的・身体的な健康問題を引き起こすリスクもあります。
このように、人材採用におけるミスマッチは、短期的にも長期的にも影響が大きく、企業として対策をしなければならないリスクなのです。
では、多くの企業で採用のミスマッチが繰り返される原因とは何でしょうか?
ここからは、採用プロセスにおいて企業と人材のミスマッチを招く原因について解説していきます。
「コミュニケーション能力が高い人」「積極性のある人材」といった抽象的な採用要件は、採用ミスマッチの最大の原因の一つです。このような曖昧な表現では、採用担当者と現場マネージャー、さらには候補者それぞれが異なる解釈をしてしまい、入社後に「思っていた人材と違う」という状況が生まれます。
具体的には、「Excel上級者」という要件でも、ピボットテーブルができるレベルなのか、VBAまで扱えるレベルなのかが明確でなければ、スキルのミスマッチが発生します。求める人物像の不明確さは、選考プロセス全体の判断基準を曖昧にし、結果として不適切な採用判断につながってしまうのです。
多くの企業で実施されている非構造化面接は、面接官の主観に左右されやすく、採用ミスマッチの温床となっています。
「第一印象が良い」「話しやすい」といった感覚的な評価が優先され、実際の業務能力や適性が正しく評価されないケースが頻発しています。また、面接官によって質問内容や評価基準が異なると、同じ候補者でも全く違う評価結果になってしまいます。
このような属人的な面接プロセスでは、候補者の本質的な能力や企業との相性を見極めることは困難です。構造化されない面接手法や、複数の観点からの評価システムの不足が、判断の精度を大幅に下げているのが現状です。
求人票や面接で業務内容やスキル要件は詳しく説明されても、企業の文化や価値観、実際の働き方については表面的な説明にとどまることが多いのが実情です。「風通しの良い職場」「チームワークを重視」といった抽象的な表現では、候補者は具体的な職場環境をイメージできません。
実際の意思決定プロセス、残業に対する考え方、失敗に対する組織の反応、昇進の基準など、日常業務に直結する企業文化の詳細が伝わらないため、入社後に「こんな会社だとは思わなかった」という事態が発生します。特に、企業が理想とする文化と現実の職場環境にギャップがある場合、このミスマッチはより深刻になります。
企業と候補者の間には、常に「情報の非対称性」が存在します。
企業側は候補者の過去の実績や面接での発言しか知り得ませんが、候補者の実際の働きぶり、ストレス耐性、チームでの立ち振る舞いなどは入社後にしか分かりません。一方で、候補者も企業の実態を完全に把握することは困難です。求人票や企業ホームページに掲載されている情報と、実際の職場環境や人間関係には差があることが多く、面接という限られた時間では真の企業文化を理解することは不可能です。
このように、お互いに情報の非対称性があることを認識した上で、しっかりと両者の「期待値」を調整していくことが必要です。とはいえ、お互いに情報が十分でない状況では、どうしてもこの「期待値調整」がうまくいかないのです。
採用現場は、いつも「時間がない」状況ではないでしょうか。
急な欠員補充や事業拡大による人員増強の必要性から、十分な検討時間が確保できないことも多く、現場からの「とりあえず人手が欲しい」というリクエストに答えるべくできる限り最短の期間で新しい人材に入ってもらいたいと考える採用担当者は多いでしょう。また、競合他社との人材獲得競争の中で、慎重に選考プロセスを進める余裕がないことも多いのが実態です。
以上、正社員の採用プロセスにおけるミスマッチの主な原因を見てきましたが、これらの多くは、企業が行う採用プロセスの構造的な問題といえます。そうした問題は、採用活動にかけられる時間や労力が限られる中で、人事担当者の努力や改善だけでは、なかなか解決できません。
そこで、こうした採用活動の「限界」を乗り越える有効な解決策として近年注目を集めているのが、副業人材や業務委託人材を活用したアプローチです。これは、企業と個人が段階的に関係を構築することで、スキルマッチとカルチャーマッチの両面でリスクを大幅に軽減できる革新的な採用戦略です。ここから具体的にご紹介していきます。
「副業・業務委託で働く」ことを正社員採用に活用するには、2つの方法があります。
一つは、副業・業務委託で働いてくれている優秀な人材がいれば、正社員で入社することを誘うというやり方。これは、正社員として入社を前提としないで働き始めた人材を対象としているので、転職意欲の有無など、両者での話し合いや確認をしていくことが必要です。もう一つは、企業も個人も正社員採用を前提として、副業・業務委託で働く期間を設けるというやり方です。
いずれのやり方でも、結果的に「まずは副業として一緒に働いてみる」ことが正社員採用のプロセスに組み込まれることになり、企業・個人の両者にとって、採用のミスマッチのリスクを減らすことができます。
いわば、副業・業務委託の期間が、入社に向けた「お試し期間」として機能するのです。
副業・業務委託による人材活用の最大のメリットは、実際に一緒に働く期間を通じて相互の適性を確認できることです。面接では分からない実務能力、コミュニケーションスタイル、問題解決アプローチ、チームとの相性などを、実際の業務を通じて評価することができます。
例えば、マーケティング人材の採用を検討する際、まずは特定のプロジェクトを3ヶ月の業務委託で依頼し、その成果と働きぶりを見て正社員化を判断するということができます。
この期間中に、企業側は候補者のスキルレベル、創造性、責任感、企業文化への適応力を実際に確認でき、候補者側も企業の方針、チーム環境、業務の進め方を体験できます。
従来の採用では「入社してみないと分からない」という不確実性が大きなリスクでしたが、副業・業務委託アプローチではこのリスクを段階的に管理できます。万が一相性が良くない場合でも、正社員雇用と比較して契約終了のハードルが低く、双方にとって負担の少ない形で関係を終了できます。
また、採用コストの観点でも大きなメリットがあります。人材紹介会社への高額な成功報酬や、大規模な採用活動にかかる費用を削減しながら、より確実性の高い人材獲得が可能になります。特に、専門性の高いポジションや、企業文化とのフィットが重要な役職においては、この手法の効果は絶大です。
副業市場には、現在の職場に満足しているものの、新しいチャレンジや副収入を求める優秀な人材が多数存在します。これらの人材は、従来の転職市場には現れないため、正社員採用のみに頼っていては出会うことができません。
副業・業務委託の形であれば、「転職は考えていないが、面白いプロジェクトがあれば参加したい」という潜在層にアプローチできます。これにより、企業の人材獲得の選択肢が大幅に広がり、より質の高い候補者プールを形成することが可能になります。
副業・業務委託からスタートする関係構築では、企業と個人の双方が「試しながら決める」ことができるため、プレッシャーが少なく、より自然な形でお互いの適性を判断できます。この結果、正式な雇用に移行した場合の定着率は格段に向上し、長期的に活躍する人材の確保につながります。
また、副業や業務委託の期間に実際に社内で働いているため、オンボーディングに失敗するリスクも下がります。チームとの関係性ができている場合には、スムーズに入社することができ、社内の負担・入社者の負担がともに低減できるというメリットがあります。
現代の優秀な人材の多くは、ワークライフバランスや働き方の柔軟性を重視しています。副業・業務委託という選択肢を提供することで、こうした価値観を持つ人材にも魅力的な働き方を提案でき、人材獲得競争において優位性を確保できます。
また、フルタイムでの雇用が困難な状況(育児、介護、他の事業との兼業など)にある優秀な人材とも協働の機会を創出でき、多様な働き方を支援する企業としてのブランディング効果も期待できます。
ミスマッチを招きやすい現行の正社員採用プロセスですが、多くのミスマッチは「実際に一緒に働いてみる」ことができれば解決できるものといえます。しかし、今の正社員採用プロセスでは、時間や労力、コストなどの構造的に、これを根本的に解決することは難しい。そんな中、いきなり正社員として雇用するのではなく、まず実際に一緒に働いてスキルや相性を見極めた上で本格雇用を検討する―この新しいアプローチには多くのメリットがあることがわかりました。
とはいえ、これまでのプロセスや組織戦略を変えていくことは難しいケースもあります。そんな場合には、まずは小さなプロジェクトから副業人材との協働を始め、その効果を実感してみることがオススメです。
例えば、3ヶ月間の特定業務プロジェクトを副業人材に依頼し、その成果と働きぶりを評価してみてください。この期間中に、候補者のスキルレベル、コミュニケーション能力、企業文化への適応力を実際に確認でき、正社員化の判断材料を得ることができます。
この手法は、前述のメリットでも触れたように、転職市場に現れない優秀な潜在層にもアプローチできるため、人材獲得の選択肢を大幅に広げます。働き方の多様化を求める現代の人材ニーズにも対応でき、企業の採用競争力向上にも寄与するでしょう。
人材不足が深刻化する今だからこそ、新しい採用戦略への転換が必要です。副業・業務委託を活用したアプローチで、採用ミスマッチのリスクを最小化し、真に企業の成長に貢献する人材との持続的な関係を築いてください。新しい採用戦略が、あなたの企業の人材課題解決の突破口となるかもしれません!
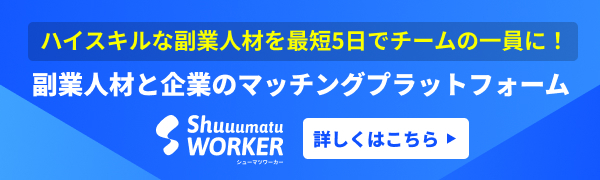
外部人材の活用について、お役立ち情報を掲載中です!