-

-
「副業」に注目が集まる社会的背景とは?在宅とリモートワークで広がる可能性
現在の日本では、各業界において人材不足が問題視されています。そんな人材不足を救うのが、在宅やリモートで働ける、副業を希望する方々です。人生のさまざまなライフステージの変化で、「時間の制約がある中でもスキマ時間に働きたい」また、「子育てしながらリモートで働きたい」というニーズは多く存在します。今回はそんな、在宅やリモートで働ける人材についてご紹介します。
2023.08.24
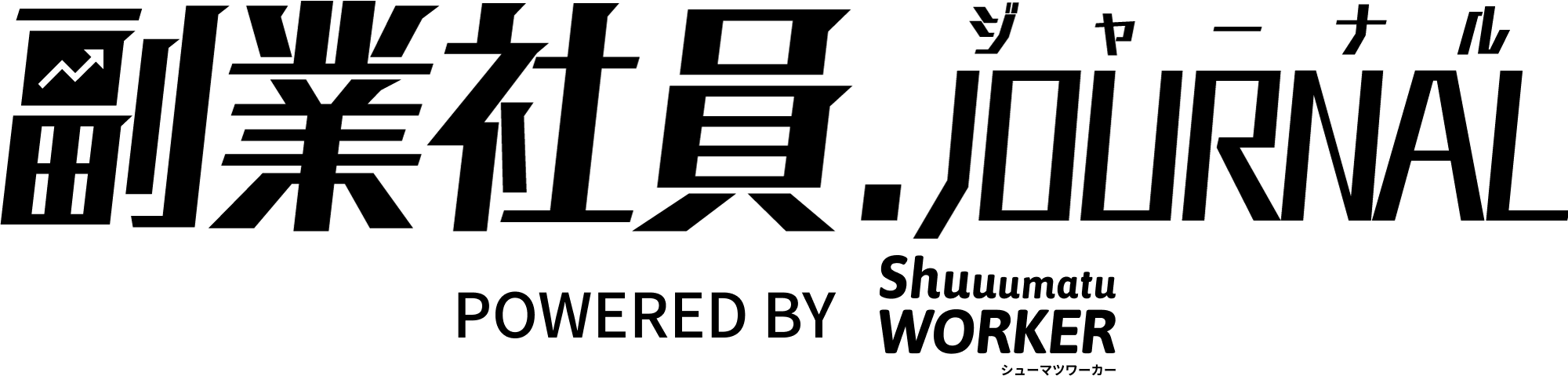
2025.11.21
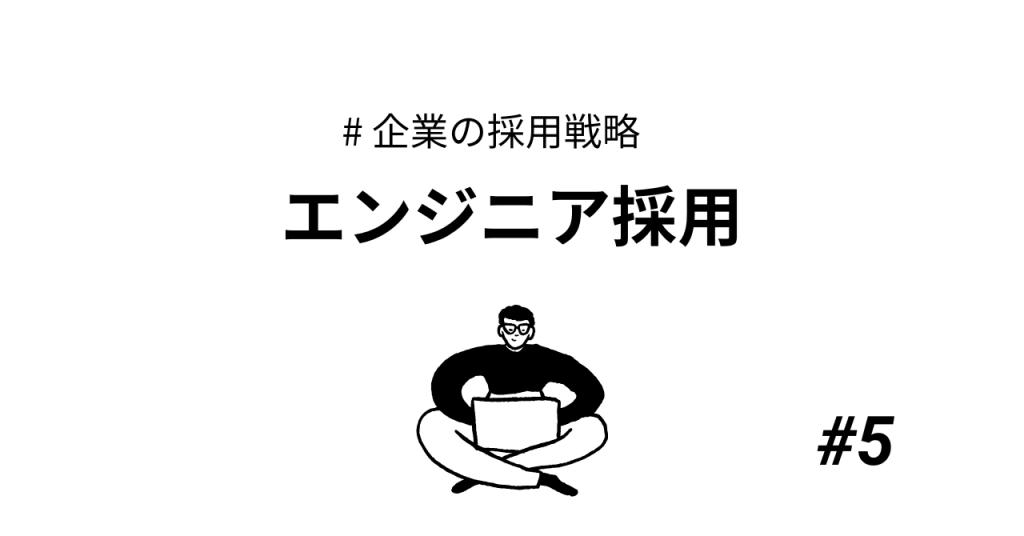
「優秀なエンジニアになかなか出会えない」
「スカウトを送っても返信がこない」
「せっかく内定を出したのに辞退されてしまう」
――エンジニア採用に携わる方の多くが、こうした悩みを抱えているのではないでしょうか。
ITエンジニアの求人倍率は10.2倍という高い水準(*1)にあるという人材エージェントによる調査もあり、経済産業省の調査報告によれば2030年には最大約79万人のIT人材が不足(*2)すると予測されています。採用競争が激化する中、従来の採用方法で求める人材を確保し続けることが難しくなっているのが現実です。
*1「ITエンジニア・クリエイター正社員転職/フリーランス市場動向 2024年6月」(レバテック株式会社)
*2 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/
「IT 人材需給に関する調査 報告書」https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf
今回の記事では、エンジニア採用における主要な課題である「スカウト」「技術試験」「オファー設計」の3つに焦点を当て、それぞれの最適化ポイントをご紹介します。さらに、これらの課題を根本的に解決する新しいアプローチとして、副業・業務委託人材の活用方法についても解説してまいります。
Contents
まずは、エンジニア採用市場の実態をデータで確認していきましょう。
2024年6月時点でのITエンジニア・クリエイターの正社員求人倍率は10.2倍という高い水準という調査があります。この数値は、あくまでも企業による実態調査・分析の結果ではありますが、1人のエンジニアに対して10社以上の企業が求人を出している計算になります。
優秀なエンジニアほど複数の企業からアプローチを受けており、企業側は常に比較されている状況であることは、多くのエンジニア採用担当の方の実感と、一致しているのではないでしょうか。
パーソルホールディングスが実施した大企業の採用実態調査(*3)によると、エンジニア採用において多くの企業が課題に挙げたのが「応募数が集まらない」で21.9%を占めているそうです。採用ターゲット層を獲得するための施策として、3分の1以上の企業(34.4%)が「給与水準の引き上げ」に取り組んでいるという結果も出ています。
*3 「大企業の採用実態調査」(パーソルホールディングス株式会社)
エンジニア採用に関して多くの企業が課題を感じているといわれています。採用担当者の工数不足や、効果的な施策を打てていないという悩みが多くの企業で共通しているようです。
多くの企業がエンジニア採用に苦戦している中、採用プロセスの各段階でどのような課題があり、どう最適化していけばよいのでしょうか。ここから具体的に見ていきます。
ダイレクトリクルーティングが主流となった現在、多くの企業がスカウトメールを活用しています。しかし、「スカウトを送っても返信がこない」という悩みは非常に多く聞かれます。
スカウトサービスによって返信率は異なりますが、一般的な総合型媒体では平均返信率は5%程度、エンジニア特化型のサービスでも16〜23%程度が目安とされています。つまり、100通のスカウトを送っても、返信があるのはわずか5〜20人程度なのです。
さらに深刻なのは、パーソナライズされていないバラマキ型のスカウトメールの場合、返信率が1%以下まで低下するケースもあることです。優秀なエンジニアほど毎日大量のスカウトメールを受け取っており、テンプレート感のあるメールは開封すらされない可能性が高いのです。
スカウトの返信率が低い主な原因は以下の3つです。
原因1:テンプレート感が強く、特別感がない
「〇〇様のご経験に興味を持ちました」といった定型文から始まるスカウトメールを、エンジニアは毎日何通も受け取っています。どの企業からも同じような内容が届くため、「自分に向けたメッセージではない」と判断され、スルーされてしまうのです。
原因2:求職者のスキルや志向性を理解していない
採用担当者がエンジニアのスキルセットや技術スタックを十分に理解せずにスカウトを送ってしまうケースがあります。例えば、フロントエンド開発者にバックエンドのポジションを提案したり、受託開発の経験者に自社サービス開発の魅力だけを伝えても、ミスマッチが生じます。
原因3:企業の魅力が伝わっていない
スカウトメールで業務内容やスキル要件は説明されても、「なぜこの会社で働くべきなのか」「どのような成長機会があるのか」といった魅力が伝わらなければ、候補者の心を動かすことはできません。特に知名度の低い中小企業やスタートアップでは、企業の独自性や魅力を明確に打ち出す必要があります。
それでは、返信率を高めるにはどうすればよいのでしょうか。具体的な改善策を3つご紹介します。
改善策1:徹底的なパーソナライゼーション
返信率を上げる最も重要なポイントは、一人ひとりに合わせたメッセージを送ることです。候補者のプロフィールやGitHubでの活動、技術ブログなどを確認し、具体的にどの経験やスキルに注目したのかを明記すると、採用担当者がどれほどそのエンジニアに注目しているかが伝わりますよね。
例えば、「〇〇様が過去に携わられた△△プロジェクトでのマイクロサービス化の取り組みを拝見しました。弊社でも現在同様の課題に直面しており、〇〇様のご経験が活かせる環境です」といった具合に、その人ならではの経験に言及することは、やはり効果的です。
改善策2:件名と送信タイミングの最適化
LAPRASの調査によると、スカウトメールの返信率は曜日や時間帯によって変動し、水曜日の返信率が高い一方、他の曜日と数%の違いが出ているとされており、時間帯では10時、午前中〜13時頃が高いという結果が出ているそうです。
*4 「4万5千件のスカウトから分析した、返信率が高い曜日と時間(2024年版)」(LAPRAS株式会社)
また、件名は具体的であることが重要です。
「エンジニア募集」といった抽象的な件名ではなく、「【リモートワークOK】BtoB SaaSベンダーにて、バックエンドエンジニア募集」のように、働き方の特徴やポジションを明確に示すことで、開封率が大幅に向上するでしょう。
改善策3:「なぜこの会社で働くべきか」を明確に伝える
企業の魅力を伝える際は、技術面だけでなく、成長機会やチームの雰囲気、働き方など、多角的にアピールすることが重要です。ただし、長文になりすぎると読まれないため、端的に「もっと知りたい」と思わせる情報量に留めましょう。
開発環境、使用技術、チーム構成、裁量の大きさ、リモートワークの可否など、エンジニアが気にするポイントを簡潔に盛り込むことで、「話を聞いてみたい」という気持ちを引き出すことができます。
スカウトから面接に進んだ後、多くの企業が直面するのが「技術試験でのスキル評価の難しさ」です。
エンジニア採用において、技術試験は候補者のスキルレベルを見極める重要なプロセスです。しかし、以下のような課題を抱える企業が少なくありません。
課題1:採用担当者のIT知識不足
人事担当者がエンジニアリングの専門知識を持っていない場合、応募者のスキルを適正に評価することが困難です。履歴書に記載された技術スタックを見ても、その深さや実務での活用レベルを判断できず、面接でも表面的な質問しかできないという状況が生まれます。
課題2:現場エンジニアの工数不足
技術試験の設計や面接の実施には、現場のエンジニアの協力が不可欠です。しかし、開発業務で多忙な中、採用活動に十分な時間を割けないケースが多く、結果として簡易的な試験しか実施できなかったり、面接の質が低下したりする問題があります。
課題3:試験内容と実務のギャップ
一般的なアルゴリズム問題やコーディングテストは実施しやすい一方で、実際の業務で必要とされるスキルセットとは異なる場合があります。例えば、難解なアルゴリズム問題を解けても、チーム開発やコードレビュー、ドキュメント作成といった実務能力が十分でない可能性もあります。
アプローチ1:段階的な評価プロセスの設計
いきなり高度な技術試験を課すのではなく、段階的に評価を深めていく方法が効果的です。まずは書類選考でポートフォリオやGitHubのコードを確認し、カジュアル面談で技術的な会話を通じて基礎力を見極めます。その後、実際のプロジェクトに近い課題を与えるという流れにすることで、評価の精度が高まります。
アプローチ2:実務に即した課題設定
アルゴリズム問題だけでなく、実際の業務で発生しそうな課題を題材にした試験を設計しましょう。例えば、既存のコードベースの改善提案や、簡単な機能追加の実装、バグ修正といったリアルなシナリオを用いることで、実務能力をより正確に評価できます。
アプローチ3:技術顧問や外部専門家の活用
社内にエンジニアリングの専門知識を持つ人材が不足している場合は、技術顧問や採用支援サービスを活用する方法もあります。ただし、コストがかかるため、長期的には社内に評価ノウハウを蓄積していくことが重要です。
優秀なエンジニアを見極め、面接を通過させても、最後のオファー段階で他社に流れてしまうケースは少なくありません。
理由1:給与水準の競争力不足
エンジニアの売り手市場が続く中、優秀な人材を獲得するには相応の給与水準が必要です。厚生労働省の調査発表では、2024年度に賃上げを実施した企業は全体の約60%で、前年度の事例を含めると約80%が賃上げを実施していることがわかっています(*5)。
*5 厚生労働省「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/24/index.html
競合他社の給与水準を把握せずにオファーを出すと、条件面で見劣りし、内定辞退につながります。特にハイスキルなエンジニアほど、複数のオファーを比較検討しており、給与は重要な判断材料となります。
理由2:働き方の柔軟性が不足している
給与だけでなく、働き方の柔軟性もエンジニアが重視するポイントです。転職希望者のニーズとしては「キャリアアップ」「年収など待遇面の改善」に加えて、「フルリモート/一部リモートワークができる環境」といった働き方の改善を求めるケースが増えています。
リモートワーク、フレックスタイム制度、副業の許可など、多様な働き方に対応できることが、企業としてのエンジニア採用の競争優位性になっていきます。
理由3:キャリアパスや成長機会が見えない
エンジニアは給与や働き方だけでなく、「技術を伸ばし、成長できる環境」「応募者自身への期待と、スキルの正確な評価」を重視しています。入社後にどのようなプロジェクトに携わり、どんなスキルが身につき、将来的にどのようなキャリアを描けるのかが明確でないと、「この会社で成長できるのか」という不安を抱かせてしまいます。
ポイント1:市場水準を踏まえた競争力のある条件提示
まずは競合他社の給与水準やオファー内容をリサーチし、自社の条件が市場と比較してどの位置にあるかを把握しましょう。必ずしも最高水準である必要はありませんが、候補者が納得できる根拠を示し、給与以外の魅力も含めた総合的な価値提案をすることが重要です。
ポイント2:働き方の選択肢を広げる
フルリモート、ハイブリッド勤務、フレックスタイム、副業許可など、多様な働き方を選択できる環境を整えることで、候補者の魅力度が高まります。特に育児や介護と両立したいエンジニアや、複数の仕事にチャレンジしたいエンジニアにとって、柔軟な働き方は大きな魅力となります。
ポイント3:具体的なキャリアパスと成長機会の提示
入社後の配属先、担当するプロジェクト、使用技術、チーム構成などを具体的に説明し、「この会社でどのように成長できるか」をイメージしてもらうことが大切です。また、技術的なチャレンジの機会、研修制度、カンファレンス参加支援など、スキルアップを支援する制度があれば積極的にアピールしましょう。
ここまで、スカウト・技術試験・オファー設計という3つの課題と最適化ポイントをご紹介してきました。しかし、これらの施策を実行しても、採用競争の激しさや工数不足といった構造的な問題を完全に解決することは難しいかもしれません。
そこで注目されているのが、正社員採用にこだわらず、副業・業務委託人材を活用するという新しいアプローチです。
メリット1:「実際に一緒に働く」ことでミスマッチを防げる
従来の採用プロセスでは、書類選考と数回の面接だけで採用を決定しなければなりません。しかし、副業・業務委託としてまず数ヶ月間一緒に働くことで、スキルレベル、コミュニケーション能力、チームとの相性などを実際の業務を通じて確認できます。
面接では分からない実務能力や企業文化への適応力を見極められるため、正社員化した後のミスマッチリスクを大幅に減らすことができるのです。
メリット2:技術試験の課題を実務で解決
面接での技術試験が「実務とのギャップ」に悩まされるのに対し、副業・業務委託であれば実際のプロジェクトに参画してもらうことで、リアルな技術力を評価できます。アルゴリズム問題を解く能力よりも、実際の開発現場でどのように貢献できるかが明確になります。
メリット3:スカウトの返信率問題を回避
副業人材マッチングサービスには、大企業で活躍する優秀なエンジニアが「新しいチャレンジ」や「スキルの幅を広げたい」という動機で登録しています。こうした人材は、転職市場には現れない潜在層であり、従来のスカウトでは出会えなかった優秀な人材にアプローチできる可能性があります。
また、副業であれば「まずは試してみる」というハードルが低いため、いきなり正社員を打診するよりも前向きに検討してもらいやすいのです。
メリット4:オファー競争から脱却できる
副業・業務委託として関係を築いた後に正社員化を提案する場合、すでにお互いの相性や働きぶりを確認できているため、給与だけが判断材料になることはありません。「この会社で働きたい」という気持ちが醸成された状態でオファーできるため、他社との条件競争に巻き込まれにくくなります。
メリット5:採用コストと採用リスクの削減
人材紹介会社への成功報酬は年収の30-35%が相場であり、年収500万円のエンジニアであれば150万円以上のコストがかかります。しかし、副業・業務委託からスタートすれば、高額な紹介手数料を支払うことなく、優秀な人材との関係を構築できます。
また、万が一相性が良くない場合でも、正社員雇用と比較して契約終了のハードルが低く、双方にとって負担の少ない形で関係を終了できます。
副業・業務委託人材の活用には2つのアプローチがあります。
アプローチ1:副業として働く中で正社員化を検討
まずは副業・業務委託として一緒に働き、お互いに相性が良いと感じたら正社員化を提案するという方法です。この場合、候補者が転職意欲を持っているかどうか、正社員化を希望しているかを丁寧に確認していくことが重要です。
アプローチ2:正社員化を前提に副業期間を設ける
企業も個人も正社員採用を前提として、副業・業務委託で働く期間を「お試し期間」として設けるという方法です。3〜6ヶ月程度の副業期間を通じて、スキルマッチ・カルチャーマッチの両面を確認した上で、正式に雇用契約を結びます。
いずれのアプローチでも、「実際に一緒に働いてみる」ことが正社員採用のプロセスに組み込まれるため、採用ミスマッチのリスクを大幅に削減できます。
「副業人材の活用」と聞くと、組織戦略の大きな変更が必要と感じるかもしれません。しかし、まずは小さなプロジェクトから始めてみることをオススメします。
例えば、新しい機能開発や技術検証といった3〜6ヶ月間の特定業務を副業エンジニアに依頼し、その成果と働きぶりを評価してみてください。この期間中に、候補者のスキルレベル、コミュニケーション能力、チームとの相性を実際に確認でき、正社員化の判断材料を得ることができます。
この手法は、転職市場に現れない優秀な潜在層にもアプローチできるため、人材獲得の選択肢を大幅に広げます。働き方の多様化を求める現代の人材ニーズにも対応でき、企業の採用競争力向上にも寄与するでしょう。
シューマツワーカーなら、多くのハイレベルエンジニアが登録する人材データベースから、御社に最適な人材「副業したい」意欲のあるエンジニアを、1週間程度で紹介してもらえます。募集内容の作成は専任の担当者が手伝ってくれますので、忙しい採用担当者にぴったりのトライアル方法です。
エンジニア採用の成功には、スカウト・技術試験・オファー設計という各プロセスの最適化が不可欠です。それぞれのポイントをもう一度振り返りましょう。
スカウトの最適化
技術試験の最適化
オファー設計の最適化
そして、これらの課題を根本的に解決する新しいアプローチとして、副業・業務委託人材の活用があります。「実際に一緒に働く」期間を設けることで、スキルマッチ・カルチャーマッチの両面を確認でき、採用ミスマッチのリスクを最小化できます。人材不足が深刻化する今だからこそ、従来の採用手法にとらわれず、新しい選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。副業・業務委託を活用したアプローチが、あなたの企業の採用課題解決の突破口となるかもしれません。
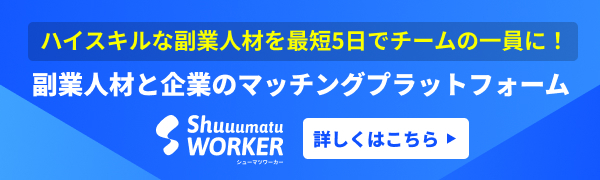
外部人材の活用について、お役立ち情報を掲載中です!