-

-
副業社員が活躍しやすい職種とその特徴とは?
年々、国内の労働人口が減少をたどる一方で、働き方はどんどん多様化しており、フリーランス…
2020.07.16
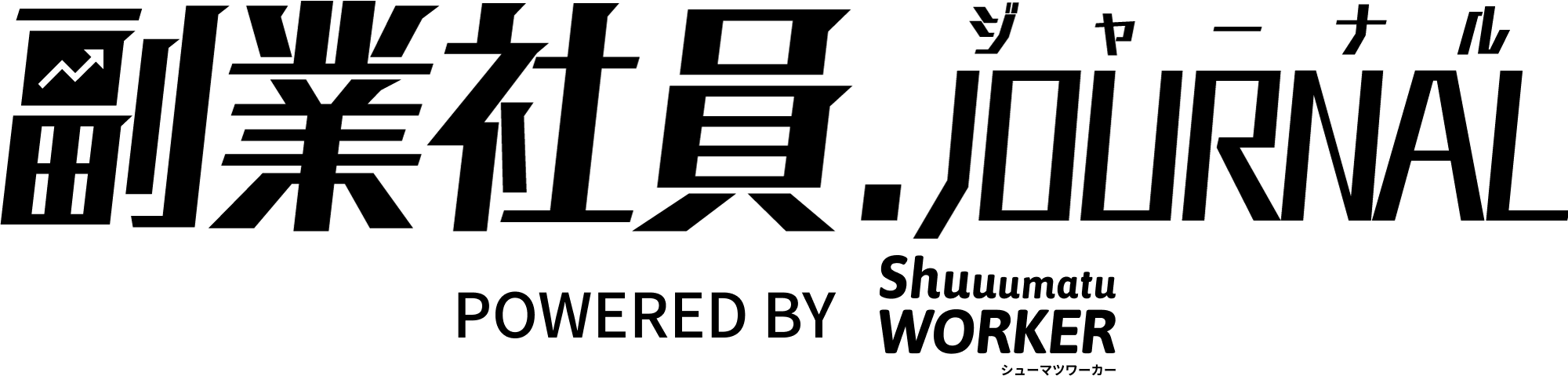
2025.11.14

「面接の日程調整だけで、何往復もメールのやり取りが必要」
「書類選考だけでも多くの時間がとられてしまう」
「採用したのに、すぐに辞めてしまった…」
採用活動において、こうした課題に直面している人事担当者の方は多いのではないでしょうか。人材不足が深刻化する中、採用業務の負担は年々増加し、限られた人員で効率的に優秀な人材を見極めることが求められています。
こうした背景の中で、近年注目を集めているのが「AI採用」。AIを活用することで、採用プロセスの効率化と精度の向上を目指して、多くの企業が導入を検討し始めています。
しかし、AI採用ツールは万能ではなく限界もあります。この記事では、AIで効率化を進めつつ、AIの限界を補うための、実践的なヒントをご紹介してまいります!
Contents
「AI採用」というのは、現在進化し続けているAIを、企業の採用プロセスの効率化・最適化に活用していく方法です。
採用活動は従来、募集要項の記載やアップデート、書類選考、候補者とのコミュニケーション、面接日程の調整、自社とのマッチ度や、業務やポジションへの適性判断・・・など、多くの“人的リソース”のかかる業務があり、採用担当者は日々忙しいことが常態化していることが多い領域ですよね。
ここでは、AIの技術を導入することで、採用活動全体のスピードと精度を向上させることを目指すことを、「AI採用」と呼んでいます。
AI採用が注目を集めている背景には、いくつかの要因があります。
第一に、「採用DX(デジタルトランスフォーメーション)」の潮流です。あらゆる業務領域でデジタル化が進む中、採用業務も例外ではありません。特に新型コロナウイルスの影響でオンライン化が加速し、採用プロセスのデジタル化が一気に進みました。
第二に、深刻な人材不足への対応です。少子高齢化により労働人口が減少(*1)する中、限られた採用リソースで効率的に優秀な人材を獲得する必要性が高まっています。特に中小企業やスタートアップでは、少人数の人事チームで大量の応募者に対応しなければならず、業務負担が限界に達しているケースも少なくありません。
*1 総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)」 https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/gaiyou.pdf
第三に、採用コストの削減圧力です。求人広告費や人材紹介手数料が高騰する中、採用プロセスを効率化することで、コストを抑えながら必要な人材を確保したいというニーズが高まっています。
採用現場でAIを活用する方法は、大きく分けて2つあります。
一つは、AI機能を搭載した専用の採用管理システム(ATM)を導入する方法、もう一つは、ChatGPTなどの汎用型AIを活用して求人票作成や応募者対応を効率化する方法です。
それでは、具体的にAIがどのような役割を果たしてくれるのか、例を見ていきましょう!
「AI採用」(AI搭載のATMの導入・汎用型AIの活用)を導入することで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは、主要な3つのメリットをご紹介します!
AI採用ツールの最も分かりやすいメリットは、採用業務にかかる時間を大幅に削減できることです。
例えば、100名の応募者の書類選考を人間が行う場合、1人あたり平均5〜10分かかるとすると、合計で8〜16時間もの時間が必要になります。これを1日で処理しようとすれば、他の業務が完全にストップしてしまいます。
しかし、AIスクリーニングを活用すれば、同じ作業を数時間で完了させることができます。AIは疲れることなく、一定の基準で正確に評価を続けられるため、大量の応募者がいる場合でも迅速に処理できるのです。
また、面接日程の調整も大きな工数削減ポイントです。従来は、候補者に候補日を提示し、返信を待ち、面接官のスケジュールを確認し、再度候補者に連絡する…という作業を繰り返す必要がありました。この作業だけで、1人あたり30分以上かかることも珍しくありません。
自動調整ツールを使えば、候補者と面接官の双方が自分の空いている時間を入力するだけで、システムが自動的に最適な日時を見つけて設定してくれます。採用担当者の手を煩わせることなく、スムーズに面接が実現します。スピーディーに採用プロセスを進めることが可能になります。
AI採用のもう一つの大きなメリットは、選考の精度が向上し、人間特有のバイアス(偏見)を排除できることです。
人間が書類選考や面接を行う場合、どうしても主観的な判断が入り込みます。「第一印象が良いから、きっと仕事もできるはず」といった、根拠のない思い込みで判断してしまうこともあります。このような「第一印象バイアス」は、本当に優秀な人材を見逃し、面接が上手なだけで実務能力が伴わない人材を採用してしまうリスクもあります。
AIは、事前に設定された客観的な基準に基づいて評価を行うため、こうしたバイアスの影響を受けません。学歴や性別、年齢などの情報を評価から除外することも可能で、純粋にスキルや経験に基づいた公平な選考が実現します。
また、データに基づいた判断ができることも大きな利点です。過去の採用データを分析し、「どのような特性を持つ候補者が入社後に活躍しているか」というパターンを学習することで、より精度の高い予測が可能になります。
AI採用ツールの導入は、応募者側にもメリットをもたらします。候補者体験(Candidate Experience)の向上は、企業の採用力強化に直結する重要なポイントです。
候補者体験の向上につながるAI活用施策例
こうした候補者体験の向上は、企業のブランドイメージを高めます。「この会社は採用プロセスがスムーズで、丁寧に対応してくれる」という印象は、内定を出した際の承諾率アップにもつながります。
採用活動は、企業が候補者を選ぶだけでなく、候補者からも選ばれる時代です。AI採用ツールを活用した優れた候補者体験の提供は、採用競争力を高める重要な要素となっています。
ここまで、AI採用のメリットを見てきましたが、AI採用ツールは決して万能ではありません。むしろ、その限界を正しく理解しておかないと、採用の失敗につながる危険性があります。
ここでは、AI採用ツールが抱える3つの構造的な限界について解説します。
AI採用ツールの最大の限界は、「企業文化との相性(カルチャーフィット)」を判断できないことです。
AIは、スキルや経験年数、資格など、数値化・パターン化できる情報の分析には優れています。しかし、「この人は自社の企業文化に合うか」「チームメンバーとうまくやっていけるか」といった、定性的で複雑な要素を評価することは難しいといえます。
カルチャーフィットの判断には、以下のような要素が必要です。
これらは、人間同士が、一緒に働くなど、時間をかけて関係を築く中で見極めることのできる要素といえます。カルチャーの言語化などに時間をかけ、明確な基準を先に設けておくなど、事前に全社的、組織的な工夫をすればある一定の効果は出せるかもしれません。しかし、候補者の人柄を判断するといった部分をAIに任せることは、今後もなかなか難しいかもしれません。
AI採用ツールのもう一つの大きな限界は、「実際の実務能力」を評価できないことです。
履歴書や職務経歴書に書かれた内容、面接での発言をAIが分析することはできます。しかし、「実際にその仕事ができるか」は全く別の問題なのです。
例えば、「プロジェクトマネジメントの経験があります」と履歴書に書くことは簡単です。面接で「過去にどんなプロジェクトを管理しましたか?」と聞かれても、上手に答えることはできるでしょう。しかし、実際に複数のステークホルダーを調整しながらプロジェクトを期限内に完遂する能力があるかどうかは、実務を通してしか確認できません。
同じ「営業」でも、新規開拓、既存深耕、インサイドセールス、フィールドセールスなど、求められるスキルは全く異なります。履歴書や面接だけでは、こうした細かいスキルセットの違いを正確に把握することは困難です。
以下のような能力は、実際の業務を通してしか評価できません。
こうした「実践力」は、書類や面接では測ることが難しく、実務の現場でしか確認できないのです。
AI採用ツールを効果的に活用するには、「どんな人材が欲しいのか」を明確に定義する必要があります。しかし、多くの企業では、ここがあいまいなままになっています。
人事担当者が現場部門から受けるリクエストで最も多いのが、「即戦力が欲しい」という言葉です。しかし、「即戦力」とは具体的にどんな人材を指すのでしょうか。
こうした具体的な定義がないまま、「とにかく即戦力」という曖昧な要件でAIツールを使っても、適切な候補者を選ぶことはできません。
「コミュニケーション能力が高い人」「積極性のある人」「マーケティングができる人」といった抽象的な表現では、AIは何をどう評価すればよいのか分かりません。例えば、「Webマーケティング経験3年以上、Google広告運用の実務経験があり、月間100万円以上の予算を管理した経験がある人」といった具体的な基準があれば、AIは正確に候補者を評価できます。
以上、AI採用ツールの3つの限界を見てきました。これらの限界を理解せずにAIツールを導入しても、採用の成功にはつながりません。では、どうすればこれらの限界を補い、AI採用ツールを最大限に活用できるのでしょうか。次の章で、具体的な解決策をご紹介します。
AI採用ツールの限界を理解した上で、それをどう補うか——ここが採用戦略の成否を分ける重要なポイントです。
結論から言えば、最も効果的な方法は「実際に一緒に働いてみる」ことです。ここで一つの方法として提案するのは、業務委託(副業含む)でのトライアル期間を設け、実務を通じてスキルとカルチャーフィットの両方を確認する方法です。
まずは、具体的なプロセスを考えてみましょう。「AI×業務委託のハイブリッド採用」の実践のための4ステップです。
まず、AIを活用した人材要件や募集要項を元に、候補者を募集します。そしてAI採用ツールを活用して、必須スキルや経験年数などの基本要件を満たす候補者を絞り込みます。従来は何日もかかっていた書類選考が、数時間で完了します。
AIでスクリーニングした候補者に対して面接を実施し、コミュニケーション能力や価値観、企業文化との大まかな相性を確認します。
ステップ3:副業として3〜6ヶ月のプロジェクトを依頼
面接で良い印象を持った候補者に、まずは「副業」(業務委託)として具体的なプロジェクトを依頼します。例えば、新規サービスのLP制作や特定機能の開発など、明確な成果物があるプロジェクトを週10時間程度の稼働で進めます。
このトライアル期間中に、以下を確認します。
ステップ4:双方が合意すれば正社員化
トライアル期間を通じて企業側も候補者側も「一緒に働きたい」という確信が持てたら、正社員採用へと進みます。双方がすでに深く理解し合っているため、入社後のギャップが最小限に抑えられます。
AIを活用して採用業務を効率化しつつ、人材の最終的な判断においては「副業」で一緒に働いてみて、候補者とすり合わせを行っていく。この方法には「AI採用」だけでは抜け落ちてしまういくつかの点において、企業にとってメリットがあります。
履歴書や面接では測れない実務能力を、実際のプロジェクトを通じて確認できます。成果物という客観的な事実に基づいて採用判断ができるのです。
AIでは判断できなかった企業文化との相性を、実際に働く中で確認できます。企業側は候補者がチームに溶け込めるかを見極め、候補者側も職場の雰囲気や働き方が自分に合うかを実感できます。
仮に相性が合わなかった場合でも、業務委託契約であれば柔軟に対応できます。トライアル期間中も成果を出してもらえるため、正社員化に至らなくてもプロジェクトの価値が残ります。
また、候補者にとっても、一緒に働いてみる期間が「副業」としての参加になるため、転職の場合に比べてはるかに低リスクで、企業との相性を見極めることができます。プロジェクトの成果が個人としての実績になるのもメリットです。
業務委託から正社員になった人材は、入社時点で既に企業文化や業務内容、チームメンバーを理解しています。通常6ヶ月かかる戦力化期間が、1ヶ月以内に短縮されたケースもあります。
「転職は考えていないが、新しい挑戦はしてみたい」という優秀な人材に、副業という形でアプローチできます。通常の採用チャネルでは出会えない人材層との接点を持てることは大きな戦略的メリットです。
AI採用ツールと業務委託でのトライアル採用は、相互に補完し合う関係にあります。
この二段構えのアプローチにより、採用プロセス全体の質とスピードを向上させることができます。
AI採用とそれを補う方法を、現状の「採用現場」に導入するには、小さく始めることがオススメです。小さく初めて成果を上げていくことで、全社的に広めていくのに、以下のようなステップをご紹介します。
AI採用ツールは「効率化」には最適ですが、カルチャーフィットの判断や実務能力の評価には限界があります。
この限界を補うために、業務委託でのトライアル採用を組み合わせることで、採用の確実性が格段に高まります。AIで効率化した採用プロセスに「実際に働いてもらう」という要素を加えることで、スキルの実証、カルチャーフィットの相互確認、採用リスクの最小化など、多くのメリットが得られます。
この戦略は特に、採用リソースが限られている中小企業・スタートアップ、専門性の高いポジションを採用したい企業、採用ミスマッチに悩んでいる企業に適しています。
まずは1つのポジションで、3ヶ月程度の小さなプロジェクトから始めてみてください。効果を確認しながら徐々に拡大していくことで、自社に最適な採用プロセスを構築できるはずです。
AI採用ツールの効率性と、業務委託での確実な見極めを組み合わせたハイブリッド戦略——これが、これからの時代の採用成功の鍵となるのではないでしょうか。採用活動の課題に悩んでいる企業様のヒントになれば幸いです!
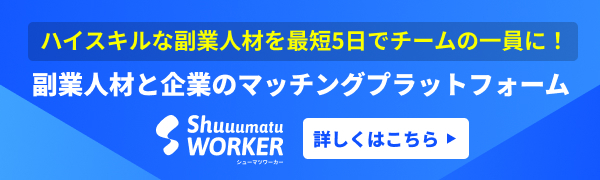
外部人材の活用について、お役立ち情報を掲載中です!